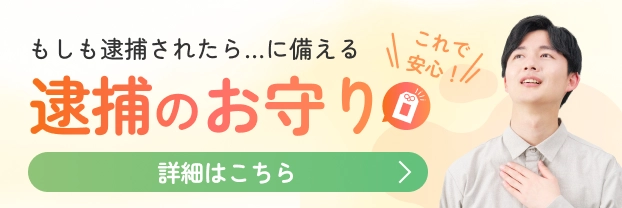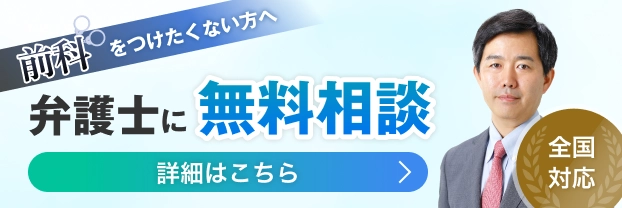- その他
- 送致
送致と逮捕では何が違う? 刑事事件の流れと送致されるケースとは


刑事事件の被疑者になると、警察から捜査を受けたあとに検察官に「送致」されることになります。
刑事事件における「送致」とはどのような手続きを指すのでしょうか?逮捕とは何が違うのでしょうか?もし自分の家族が刑事事件を起こしてしまったら、送致の意味を理解するとともに、適切な行動を起こすことが大切です。
本コラムでは「送致」をテーマに、逮捕や送検との違い、送致されるまでから送致されたあとの刑事手続きの流れについて解説します。逮捕・送致された場合に弁護士ができる活動についても確認しましょう。
1、送致と逮捕の違い
送致の意味や逮捕との違いについて解説します。
-
(1)送致の意味
「送致」(または検察官送致)とは、警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐことをいいます。
刑事事件では、第一次的に警察が捜査を行い、検察官に送致します。送致を受けた検察官は自らも捜査を行い、起訴・不起訴を判断するという流れで手続きが進められます。 -
(2)送致と送検の違い
送致と似た言葉で「送検」があります。これはテレビ局や新聞社などの報道機関が送致を指すときに使う報道用語です。報道機関では、警察で拘束した被疑者の身柄を検察官に引き渡すことを「身柄送検」、警察が被疑者の身柄を拘束せず捜査書類や証拠のみを検察官に引き継ぐことを「書類送検」と使い分けているようです。
いずれも一般の方には送致よりも聞き慣れた言葉かもしれませんが、法律用語ではありません。正しくはどちらも送致です。 -
(3)送致と逮捕の違い
送致は警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐ手続きのことですが、「逮捕」とは、刑事事件の被疑者の身柄を拘束する手続きをいいます。
逮捕は被疑者による証拠隠滅または逃亡を防ぐために行われます。つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は、逮捕は行われず、在宅のまま捜査が進められます。
このように被疑者の身柄を拘束せずに捜査する事件を「在宅事件」といい、逮捕して捜査する「身柄事件」と区別されています。一般に刑事事件を起こすと必ず逮捕されると認識している方も多いですが、必ずしも逮捕されるわけではありません。犯罪白書によれば、令和元年度における検察庁既済事件の被疑者のうち、身柄拘束をともなう人員数の割合は35.7%にとどまっています。 -
(4)逮捕の種類
逮捕には以下の3種類があります。
● 通常逮捕
裁判官が発付した逮捕状にもとづき行われる逮捕のことをいいます。警察官などが逮捕状を被疑者の面前に示し、被疑事実と逮捕の理由などを告げたうえで逮捕します。
● 現行犯逮捕
犯罪が行われている最中や、犯罪の直後に実行される逮捕をいいます。現行犯に限っては被疑者を取り違える可能性が比較的低く、急速な逮捕の必要性が認められるため、逮捕状は不要です。
● 緊急逮捕
一定の重大犯罪にあたり、急速を要するため逮捕状を請求する時間がない場合に、逮捕の理由を告げたうえで行う逮捕です。逮捕した警察官などは、逮捕のあと直ちに逮捕状を請求しなければならず、裁判官が逮捕状を発付しない場合は被疑者の身柄は釈放されます。 -
(5)逮捕できるのは誰か
刑事訴訟法第199条第1項の定めによれば、被疑者を逮捕できるのは「検察官」「検察事務官」「司法警察職員」です。また現行犯に限っては私人による逮捕も認められています(刑事訴訟法第213条)。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
2、送致されるケースと送致されないケース
どのようなケースで送致されるのか、また送致されないケースはあるのかについて解説します。
-
(1)原則として送致される
刑事訴訟法第246条には、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」とあります。
つまり、警察が刑事事件の捜査をしたときは、原則として送致します(全件送致主義)。身柄事件、在宅事件のどちらであっても扱いは同じです。 -
(2)追送致されるケース
追送致とは、余罪が発覚した場合に、余罪について事件の書類と証拠のみを送致することをいいます。たとえば窃盗事件で逮捕された被疑者が、取り調べ中に別の窃盗事件についても自白したので捜査したところ、余罪についても容疑が固まったため送致するのが追送致です。
余罪があっても再逮捕されずに追送致される可能性があるのは、余罪について自白をしている、余罪が軽微な事案であるなどのケースです。ただし、最初に立件された事件で逮捕されている場合は、追送致をもって身柄を釈放されるわけではなく、最初の事件については原則通り身柄つきで送致の手続きが進められます。 -
(3)送致されないケース
全件送致主義を定めた刑事訴訟法第246条但書には、「ただし、検察官が指定した事件については、この限りでない」と規定されています。
つまり、例外的に送致されないケースが存在します。「微罪事件」と呼ばれる事件です。
微罪事件については、検察官において特に立件しない限り、当該事件で起訴されることはありません。そのため、微罪事件について送致しない手続きをとることは、「微罪処分」と呼ばれています。
微罪処分とは、事件を検察官に送致せず、警察限りで終わらせる処分をいいます。微罪処分になると検察官に送致されないので、起訴されることも刑事裁判を受けることもなく、事件がそこで終了します。
ただし、全件送致が原則なので、微罪処分はごく限られたケースで受ける処分だと思っておきましょう。 -
(4)送致後に身柄が釈放されるケース
送致されても以下のケースでは身柄が釈放されます。
- 検察官が勾留請求をしなかった
- 検察官が勾留請求をしたが、裁判官が勾留を認めなかった
「勾留」とは、送致のあと、さらに捜査を尽くす必要がある場合に被疑者の身柄を引き続き拘束する手続きをいいます。勾留は被疑者の身柄を最長で20日間の長期にわたり拘束する手続きなので、検察官が請求したうえで、裁判官が勾留を認めるか否か判断します。
勾留の要件は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、次のいずれかひとつにあたる場合です(刑事訴訟法第207条、第60条)。- 定まった住居を有しないとき
- 罪障隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 逃亡し、または逃亡をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
身柄が釈放されると、そのあとは在宅事件として捜査が進められます。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、送致されるまでの流れ
刑事事件を起こしてから送致されるまでは、どのような流れで手続きが進められるのでしょうか?
-
(1)捜査機関の捜査
事件が発覚すると、警察や検察などの捜査機関が捜査を開始します。事件が発覚するきっかけは、被害者による被害届の提出や告訴、第三者の告発、目撃者の通報などがあります。
捜査機関は事件の真相を明らかにするために、目撃者や関係者などに聞き込みをする、被疑者に任意の事情聴取を行う、被疑者が罪を犯したことを裏付けるための証拠を集めるなどの捜査を実施します。
裏付け捜査などによって犯罪の嫌疑が固まると、捜査機関は被疑者が逃亡や証拠隠滅のおそれがある(逮捕の必要性)と判断した場合には、裁判官に逮捕状を請求します。逮捕の必要性がなければ、被疑者を逮捕しないまま任意同行を求め取り調べるなどして捜査を続けます。 -
(2)逮捕
身柄事件、すなわち逮捕される事件では、多くのケースでは警察官に、事件によっては検察官に逮捕されます。
逮捕されたあとの身柄拘束には法律上の期限があります。警察が逮捕した場合、警察は逮捕から48時間以内に取り調べを行い、被疑者の身柄と事件書類・証拠物を検察官に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官はさらに取り調べを行い、送致から24時間以内に被疑者の身柄を釈放するか、裁判官に勾留を請求するのかを判断します。つまり、警察が逮捕した事件では、逮捕から釈放または勾留請求までの期限は「72時間」です。
ここまでの72時間は、被疑者は原則として外部との連絡や面会が認められません。
一方、検察官が逮捕した場合は、検察官は逮捕から48時間以内に取り調べを行い、被疑者の身柄を釈放するか、裁判官に勾留を請求するのかを判断します。警察から検察官に事件を引き継ぐ送致の手続きはないため、警察が逮捕した場合よりも24時間分手続きの時間が短くなります。
なお、検察官が逮捕した場合の48時間も、原則として被疑者は外部との連絡や面会は認められません。 -
(3)在宅事件における送致までの流れ
逮捕されない在宅事件では、身柄事件のように送致までの時間制限がありません。警察は捜査が終了した時点で事件の書類と証拠物を検察官に送致します。
警察は被疑者を送致するか、送致するとしていつ送致するのかを積極的に教えてくれるわけではありません。いつ送致されるか分からないため、精神的に不安な状態が続くでしょう。送致までの時間制限がないため事件が長期化する可能性もあります。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
4、送致されたあとの流れ
続いて、検察官に送致されたあとの手続きの流れも確認しましょう。
-
(1)捜査が進む
被疑者が送致されたあとは、前述の通り検察官の捜査・取り調べが行われます。送致は警察から検察官に事件を引き継ぐ手続きですが、事件が警察のもとから完全に離れたわけではありません。送致のあとも、検察官の指示により、警察の捜査が進められる場合があります。
送致から24時間以内に、検察官は被疑者を釈放するか、勾留を請求するかを決定します。 -
(2)勾留請求・勾留決定
検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留を認めた場合は、原則10日間、延長されると追加で10日間身柄拘束が続く可能性があります。
検察官が勾留を請求しなかった場合や裁判官が勾留を認めなかった場合は、身柄を釈放され、在宅事件に切り替わります。 -
(3)起訴または不起訴
勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決定します。勾留されたまま起訴された場合は、およそ1~2か月後に開かれる刑事裁判まで引き続き身柄を拘束されます。
一方、不起訴になった場合は即日で身柄を釈放され、自宅に帰されます。事件はそこで終了し、新たな証拠が見つかるなど特別な場合を除き、原則として起訴されることはありません。起訴されないので刑事裁判が開かれることも、刑罰を言い渡されて前科がつくこともありません。
なお、検察官が起訴とするか不起訴とするか判断せずに、身柄を釈放する場合もあります。この場合は、在宅で捜査がしばらく続き、それを踏まえたうえで、起訴とするか不起訴を判断することになります。 -
(4)保釈
逮捕・勾留されたまま起訴されると原則として刑事裁判まで引き続き身柄を拘束されますが、起訴後は「保釈」を請求できます(刑事訴訟法第88条)。保釈が認められた場合は、身柄を釈放され、自宅で生活しながら公判の日に出廷して審理を受けることになります。
ただし、あくまでも保釈は裁判が結審するまでの一時的な身柄の釈放です。裁判で実刑判決を言い渡された場合には、再度身柄を拘束されたうえで刑に服すことになります。 -
(5)刑事裁判
刑事裁判では、裁判官が被告人を有罪または無罪にするか、有罪の場合はどのくらいの刑に処すのかを決定します。有罪の場合の刑は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料のいずれかで、犯した罪によって決まります。どの刑を言い渡された場合でも、仮に判決に執行猶予がついたとしても、前科がついた状態になります。
無罪の場合は身柄を釈放され、前科もつきません。一事不再理の原則により、新たな証拠が見つかった場合でも、同一の事件で再び刑事裁判にかけられることはありません(憲法第39条、刑事訴訟法第337条)。
なお、裁判には主に正式裁判と略式裁判の2種類があります。正式裁判は公開の場で開かれる裁判のことです。略式裁判は簡易裁判所が管轄する100万円以下の罰金または科料に相当する事件について、書面のみで審理される簡略化された裁判をいいます。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
5、少年事件における送致
20歳未満の少年(少女も含む)が起こした事件は、いわゆる少年事件と呼ばれています。少年事件における送致は以下の場面があります。
-
(1)被疑者段階
14歳以上の少年が、罪を犯した場合には、少年であっても刑事訴訟法が適用されます(少年法第40条)。そのため、この場合には、少年を成人と同様、逮捕・勾留される可能性があります。
警察に逮捕された場合は、48時間以内に捜査・取り調べを受けたうえで、検察官に送致されます。送致を受けた検察官は24時間以内に捜査・取り調べを行い、さらに捜査を尽くす必要があると判断した場合は、裁判官に対して「勾留」または「勾留に代わる観護措置」を請求します。
勾留は成人の事件と同様に身柄を拘束される措置を指しますが、成人の場合と異なり、前述の勾留の要件のほかに「やむを得ない場合」である必要があります(少年法第48条第1項、第43条3項)。「やむを得ない場合」か否かは、勾留により少年絵及ぼす悪影響、捜査の遂行の必要性などから判断されますが、実際上は、成人とほとんど変わらない運用をされています。
勾留に代わる観護措置は少年法第43条にもとづき、少年を少年鑑別所で検察官が請求をした日から最長10日間拘束する措置をいいます。勾留または勾留に代わる観護措置が満期を迎えるまでに、検察官は少年の処分に関する意見を付したうえで、事件を家庭裁判所へ送致します。 -
(2)家庭裁判所への送致
少年が刑事事件を起こすと、警察の捜査・調査を受けたあと、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、犯罪の軽重や身柄・在宅事件にかかわらず、すべての事件が家庭裁判所へ送致されます(少年法第41条、第42条)。これは全件送致主義といわれています。
少年事件が家庭裁判所へ送致されるのは、少年法が少年の健全育成を目的としているからです。少年は精神的に未成熟であるため周囲の影響を受けやすく、事件の客観的な側面だけで少年の犯罪性を判断することは困難です。
そのため成人と同じように刑罰を科すのではなく、専門的な調査機能をもつ家庭裁判所が本人の資質や家庭環境などを調査したうえで個々の少年に適した処分を決定し、社会の一員としてふさわしい人間となるための矯正、教育を与えるのが適切だと考えられているのです。
送致を受理した家庭裁判所は、24時間以内に少年を観護措置にするか、審判不開始または在宅観護にするかを決定します。観護措置とは、家庭裁判所に送致された少年を審判にかけるべきかを調査するために、少年の身柄を少年鑑別所に収容する措置をいいます。
観護措置の期間は原則2週間ですが、継続の必要がある場合には、1回更新することはできます(少年法第17条第3項、第4項本文)。また、死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件については、さらに追加で2回を限度として更新することができるとされています(少年法第17条4項但書)。
観護措置のあいだ、家庭裁判所の調査官によって少年の家庭環境や交友関係、資質などに関する調査が行われ、裁判官は少年を少年審判に付するか審判不開始にするのかを決定します。少年審判では、保護処分や知事・児童相談所長送致、検察官送致(逆送)などの処分を言い渡されます。 -
(3)検察官送致(逆送)
家庭裁判所へ送致されたあと、家庭裁判所からさらに検察官へと送致される場合があります。検察官送致は、刑事処分が相当だと判断されたことによるものと、年齢超過を理由にしたものがあります。
● 刑事処分が相当だとみなされた場合の検察官逆送
14歳以上の少年が死刑、懲役、禁錮にあたる罪を犯した場合で、成人と同様に刑事処分に付すべきと判断された場合は検察官に逆送されます。また、事件を起こしたときに16歳以上で、故意の犯罪行為により人を死亡させた場合は、原則として検察官に逆送されます(少年法第20条第2項本文)。逆送された少年は原則として起訴され、成人と同じように刑事裁判にかけられます。
なお、14歳未満の少年は刑法第41条の規定により刑事責任能力がないとみなされているため逆送されることはありません。
● 年齢超過を理由にした検察官逆送
家庭裁判所へ送致され、調査や審判を行っている段階で年齢が20歳以上であることが判明した場合も、検察官へ逆送されます。年齢を判断するのは事件を起こしたときではなく、調査・審判の時点です。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
6、逮捕・送致された場合の弁護活動
自分の家族が逮捕・送致されてしまったら、ご家族は速やかに弁護士へ相談しましょう。弁護士は次のような活動を通じてサポートします。
-
(1)被疑者との接見(面会)
逮捕から72時間以内はたとえ家族であっても被疑者本人と面会することはできません。逮捕された本人の様子を知ることや、事件が真実かどうかを本人の口から聞くことさえもかなわず、ご家族は不安でたまらないでしょう。当然、逮捕された本人も孤独と不安の中で精神的につらい状況に置かれるはずです。
しかし弁護士だけは逮捕直後から本人と面会できます。本人に今後の見込みや弁護士がサポートする旨を伝えて安心させるほか、ご家族との連絡の橋渡しになることができます。 -
(2)取り調べのアドバイス
逮捕段階の取り調べで供述した内容は、刑事裁判になった場合に証拠として採用される可能性が高いため、取り調べで何を供述するのかは極めて重要です。捜査機関のプレッシャーに負けて、やってもいないことまで認める供述をしてしまえば、そのあとの処分が不利にはたらくおそれがあります。
弁護士であれば時間的な制約なく本人と面会し、取り調べの注意点や、被疑者に認められた黙秘権、署名押印拒否権などの権利について的確なアドバイスを与えられます。 -
(3)不起訴処分に向けた活動
送致のあとに起訴されてしまうと、わが国の刑事司法においては、非常に高い確率で有罪判決を言い渡される現実があります。そのため不起訴処分を得ることが極めて重要です。不起訴になれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。
不起訴のうち起訴猶予と呼ばれる処分は、罪を犯したのは明らかであっても、諸事情を考慮して検察官があえて起訴しないとするものです。
そのため罪を犯したのが事実でも不起訴となる可能性があります。弁護士が検察官に対して、被害者と示談が成立していること、再犯を防止するための環境が整っていることなどの有利な事情について、客観的な証拠とともに主張します。 -
(4)勾留の阻止
逮捕・送致後に勾留されると長期にわたり身柄を拘束され、会社や学校、家庭など社会生活へ与える影響が大きいため、勾留を阻止する必要があります。
弁護士は検察官・裁判官との面談や意見書の提出を通じて勾留の必要性がない旨を主張するなど、勾留を阻止するためにはたらきかけます。裁判官が勾留を決定した場合も、不服申し立ての手段である準抗告によって勾留決定の取り消しを求めます。 -
(5)被害者との示談交渉
被害者が存在する事件では、被害者との示談を成立させることが重要です。示談が成立すると、一定の被害回復が実現し、被害者の処罰感情も低下したとして、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。起訴された場合でも被告人に有利な事情として考慮され、執行猶予つき判決や刑の減軽を得られる可能性が生じるでしょう。
しかし、犯罪の被害者は被疑者に対して嫌悪感情や処罰感情を抱いているのが通常であり、被疑者本人はおろか、ご家族による示談交渉も困難です。そもそも被害者の連絡先を知らないケースも多く、捜査機関が連絡先を教えてくれることもありません。
第三者の立場であり、守秘義務もある弁護士であれば、被害者の感情をやわらげ、示談を成立させられる可能性があります。捜査機関を通じて被害者とコンタクトをとり、弁護士に限って連絡先を教えてもらえる場合もあるため、示談交渉は弁護士に一任するべきです。 -
(6)保釈に向けた弁護活動
逮捕・送致されたあとに起訴されてしまうと、被告人として勾留されるため、刑事裁判が結審するまで引き続き身柄を拘束されてしまいます。逮捕段階からの拘束期間を含めると数か月にわたり社会から隔離されるため、社会生活への影響は避けられません。
しかし、起訴後の保釈が認められると一時的とはいえ身柄を釈放されるため、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。
保釈が認められるためには、裁判官に対し、保釈の要件を満たしていること、たとえば証拠隠滅のおそれがない、被害者や証人に接触して身体や財産に害を加えるおそれがないことなどを具体的に示す必要があります。
保釈請求は、法律上では本人やご家族にも可能ですが、実際に保釈を実現させるには弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
7、まとめ
刑事事件の被疑者になると、身柄事件・在宅事件にかかわらず、原則として検察官に送致されます。全件送致主義にもとづき送致を防ぐのは困難ですが、送致されたあとの対応によって身柄拘束の期間や最終的な処分が大きく変わる可能性があります。そのため自分の家族が被疑者になった場合は早急に弁護士に相談し、身柄釈放のための活動や被害者との示談交渉など、適切な弁護活動を展開してもらいましょう。
特に逮捕された場合は制限時間内に手続きが進められてしまうため、時間との勝負になります。
刑事弁護の実績豊富なベリーベスト法律事務所が全力でサポートしますので、できるだけお早めにご連絡ください。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。