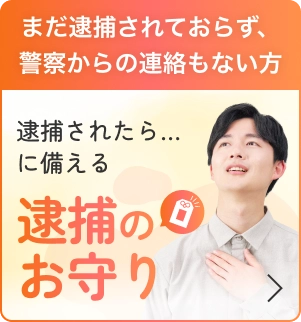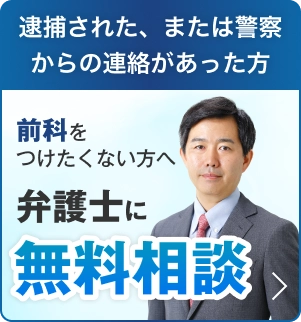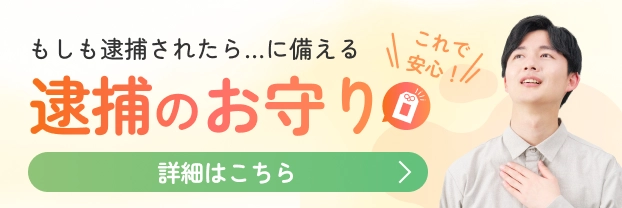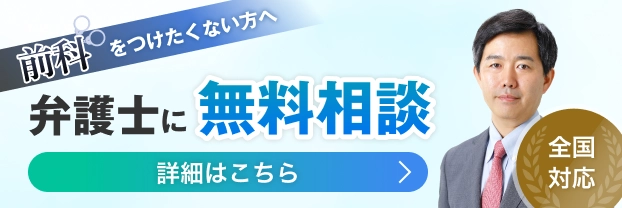- その他
- 留置場
留置場とは? 収容される期間や生活、家族にできることを解説


家族が逮捕されてしまった場合、「今どのような状況に置かれているのか」「どんな場所で過ごしているのか」などを知りたいと思うでしょう。
逮捕された本人は「留置場」と呼ばれる施設で身柄を拘束され、捜査機関からの取り調べを受けることになります。では、留置場とは具体的にどのような施設で、収容された場合にどのような生活を送ることになるのでしょうか?
このコラムでは、「留置場」について拘置所・刑務所との違い、留置場に収容される期間、留置場内での生活、留置場から釈放されるためにどのような準備が必要なのかをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、留置場とは
留置場とは、どのようなときに収容される場所なのでしょうか。基本的な概要から確認します。
-
(1)留置場とは
「留置場」とは、刑事事件の被疑者が逃走や証拠隠滅を図らないように、一時的に身柄を収容する施設です。そのほとんどが全国の警察署の建物内に設置されており、令和5年4月1日時点で1,055の施設があります。
現行の刑事収容施設法や警察庁の資料などでは「留置施設」と表記されていますが、一般的に旧監獄法の呼称である「留置場」と呼ばれるケースがほとんどです(なお、まれに「留置所」と記されていることがありますが、これは誤った表記です)。 -
(2)どのようなときに収容される施設なのか
留置場へ収容されるのは「逮捕」されたときです。逮捕された被疑者は留置場で身柄の拘束を受け、必要に応じて取調室に移動して取り調べを受けます。
「留置場へ収容された人=犯罪者」のイメージがあるかもしれませんが、逮捕によって留置場に収容されている状態では、有罪が確定していません。留置場に収容されているのは「犯罪の疑いがある人」であり、「犯罪者である」とはいえないのです。 -
(3)保護室との違い
留置場と間違えやすいのは、同じく警察署内にある「保護室」です。これは「精神錯乱に陥っている」、「泥酔している」などの状態の人を一時的に保護するための部屋です。
留置場のように犯罪の被疑者を収容する場所ではないので、家族などの身元引受人が来て手続きをすれば原則としてすぐに自宅へ帰されます。
2、留置場と拘置所の違い
留置場と混同しやすい施設に「拘置所」があります。留置場と拘置所の違いや実情を見ていきましょう。
-
(1)拘置所とは
「拘置所」とは、刑事事件の被疑者や被告人が逃亡や証拠隠滅を図らないように、身柄を拘束しておくための施設です。被疑者が起訴されると、拘置所に移送されます。留置場が全国に1055カ所あるのに対し、拘置所は全国に8カ所しかありません。
拘置所には、死刑が確定した者が収容されることもあります。死刑囚は死刑が刑罰なので、懲役刑の受刑者のように刑務所で労役に服す必要がないからです。
拘置所は犯罪の疑いがある人の身柄を収容するという点で留置場と共通していますが、管轄が違うため運用が異なります。拘置所の管轄は「法務省」です。警察が管轄する留置場と異なり、同じ施設内に取り調べを担当する警察官はいません。 -
(2)留置場で身柄を拘束されることの問題点
警察官が犯罪捜査を迅速に遂行するためには、取調室に近接した場所に留置場があることが有利にはたらきます。
一方で、被疑者側から見たときには、取り調べがおこなわれる警察署内で身柄拘束を受けたうえで、長時間におよぶ取り調べや、処遇のコントロール(食事を与えないなど)によって、自白の強要や冤罪につながるといった不利な面も指摘されています。
ただ、現在では被留置者の人権を保障するために、処遇をコントロールすることは禁止されています。また、留置部門と捜査部門の分離も徹底されているため、このような不利益は解消されてきています。
万が一不当な扱いを受けた場合は、弁護士に相談すれば不服申し立てなどによって抗議することも可能です。 -
(3)被疑者の多くは留置場に勾留されるのが実情
刑事訴訟法では、被疑者の勾留場所を拘置所(刑事施設)にすると定められていますが(第64条など)、刑事収容施設法第15条1項では勾留される者を「刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる」としています。
警察の留置場に被疑者を勾留できる権限は「代替収容制度」に決められています。
これにより裁判官は諸事情を考慮し、被疑者の身柄を拘置所と留置場のいずれかに収容する決定をおこないます。
留置場と拘置所の数を比べると圧倒的に留置場の数が多いこと、拘置所の新設が予算や周辺住民の反対などにより困難であることなどから、実際には拘置所ではなく留置場に収容される被疑者が大半であることが実情です。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、留置場と刑務所の違い
刑事事件を起こした人が収容される施設には、留置場や拘置所のほかに「刑務所」もあります。留置場と刑務所はその目的が大きく異なります。
留置場は、原則として「起訴される前の被疑者」を収容し、逃亡や証拠隠滅を防止することを目的とした施設です。刑の執行を目的としていないため、労役を課されることはありません。ただし、逃亡・証拠隠滅を防止する観点から、面会や服装など大きく制限される事柄もあります。
これに対して刑務所は、「自由刑(懲役・禁錮・拘留)が確定した受刑者」を収容して、処遇をおこなうための施設です。
刑務所の目的は、刑の執行と規則正しい生活を通じて、更生および社会復帰を促進することです。刑務官の指導は厳しく、受刑者は生活や髪型、服装などすべてにおいて大きな制限を受けます。
自由刑の大部分を占める懲役執行者には労役も課されます。受刑者は労役により、勤労意欲を高め、職業に有用な知識やスキルを身につけたうえで社会復帰を目指すことができます。
また、留置場に収容される期間は比較的短期であるのに対し、刑務所では刑期が満了するか仮釈放までの数か月、数年、数十年といった長期にわたって収容されます。
4、留置場に収容される期間・長さは?
留置場に収容される期間は、「釈放されるまで」か「起訴されて拘置所へ移送されるまで」の間です。
-
(1)最短で逮捕から48時間
逮捕された被疑者は、警察から48時間以内に取り調べを受け、検察庁へ送致されます。
送致された後は、24時間以内に検察官からも取り調べを受けます。ここまでの72時間以内に起訴・不起訴が決定します。
犯罪の捜査をした警察は、事件を原則として送致しますが、誤認逮捕などの事情があればおこなわれません。したがって、留置場で生活する期間は最短で48時間以内です。警察が取り調べの必要がないと判断すれば、48時間経過前でも釈放される可能性があります。 -
(2)最長で逮捕から23日
逮捕段階の72時間以内という短い時間では、起訴・不起訴を判断するための材料がそろわないことがあります。この場合、検察官は引き続き被疑者の身柄を拘束して捜査をするために、裁判官に「勾留」を請求します。
裁判官が勾留を認めると勾留請求の日から最長で20日間の身柄拘束が続き、勾留期間が満期を迎えるまでに検察官はもう一度、起訴・不起訴を判断します。
起訴されると拘置所へ移送されることが多く、不起訴となると釈放されます。したがって、留置場で生活する期間の最長で23日間となることが多いといえるでしょう(逮捕段階72時間+勾留段階20日間)。 -
(3)起訴後にも留置場に収容される場合がある
被疑者が起訴されると、被告人へと呼び名が変わると同時に、勾留場所も留置場から拘置所へ移されるのが原則です。しかし、拘置所が満員で空きがないなどの事情から、起訴された後も引き続き留置場に収容されるケースもあります。
もっとも、勾留場所が原則と違うからといって、被告人が置かれた立場が変わるわけではありません。起訴された後は刑事裁判を待つ身となります。
5、留置場での生活とは?
留置場では、基本的に数人と一緒の「雑居」と呼ばれる共同室で過ごすことになります。
-
(1)1日のスケジュール
各留置場でスケジュールに多少の違いはありますが、ここでは典型的なスケジュールを紹介します。
午前6時半頃に起床、洗顔や布団の片付け・掃除などをおこない、午前7時頃に朝食をとります。朝食の後には30分程度の運動の時間があり、午後0時頃に昼食、午後5時頃に夕食、午後9時頃には就寝するという流れです。
日中は、警察官や検察官からの取り調べや弁護士や家族と面会があります。それ以外の時間は刑務所のような労役はなく、本や雑誌、家族からの手紙を読むなど、ほかの被留置者の迷惑にならないように過ごします。 -
(2)食事内容
食事は朝・昼・夕の3食、健康を維持するのに必要な栄養とカロリーが備わったメニューが提供されます。
これまで健康的な食事をしていた人にとっては十分な量ですが、好きな物だけ食べていた人には物足りなさを感じるかもしれません。
通常のメニューは税金で提供されるため、食事代を支払う必要はありません。
ただし、苦手なおかずが多い人や量が足りない人などは、別の食事やお菓子、乳製品などを追加で頼むこともできます(自費での購入)。
自費で購入する場合、逮捕の際に現金をあまり持っていなかったのであれば、家族から現金を差し入れてもらう必要があります。 -
(3)入浴や洗濯
入浴は夏場と冬場で多少異なりますが、少なくとも5日に1回以上、原則として週に2回しか入れません(時間は20分程度)。
洗濯は自分でおこなったり、クリーニング業者へ委託したりすることはなく、留置場の職員がおこないます(週1回程度)。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
6、留置場での面会・差し入れ・連絡におけるルール
留置場へ収容された本人のために、家族は面会や差し入れができます。ここでは面会や差し入れのおおまかなルールや本人と連絡をとる方法について解説します。
-
(1)家族が面会できるのは勾留段階から
逮捕直後の「72時間」は、たとえ家族であっても被疑者と面会できません。
弁護士であれば逮捕直後から面会できるので、家族が逮捕段階で本人の様子を知りたい場合は代わりに面会してもらう必要があります。勾留段階に入ると、通常は家族が面会できるようになります。 -
(2)面会可能な日時や面会室の様子
被疑者と面会できる回数は1日につき1回です。ほかの希望者も含めた回数なので、すでに誰かが面会している日には、家族の面会はかないません。
面会の予約はできないため、当日に直接受付をします。ただし被疑者は実況見分や検察庁での手続きなどで留置場にいない場合があるため、事前に留置場に電話をして、本人が留置場にいることは確認しておく必要があります。
面会可能な日時は平日の午前8時30分から午後4時まで、時間は15~30分程度です。
面会室に入る際には、携帯電話や録音機などの持ち込みは禁止されており、入室前に所持品の確認を求められます。面会室での会話は基本的に自由ですが、警察官の立ち会いがあり、事件に関する話が制限される場合があります。
面会の日時やルールは留置場によって若干の違いはありますが、おおむねこのような制限があると思っておきましょう。 -
(3)差し入れできる物や手続きの方法
留置場での生活は多くの不便を強いられるため、これを少しでも緩和させるための「差し入れ」が可能です。差し入れできる品目や数量などは留置場によって異なるため、事前の電話確認が必要です。
面会時に直接手渡すことはできないので、施設の窓口で所定の用紙に記入のうえ手続きをおこないます。【差し入れできる物の例】- 衣服や下着
- メガネ・コンタクトレンズ
- 本、雑誌
- 家族からの手紙、写真
- 現金
- 歯ブラシ など
【差し入れできない物の例】- 食べ物、飲み物
- タオルやハンカチ
- 靴
- 薬
- たばこ など
なお、本や雑誌でも週刊誌などのようにホチキスが使用されているものや、衣服・靴でもひもが使用されているものは事前に取り外しておかなければなりません。
差し入れの際も細かいチェックを受けることになるので、警察署に問い合わせてその内容を確認する必要があります。 -
(4)被疑者と連絡をとりたい場合
被疑者の携帯電話は逮捕された際に押収されるか、留置場に収容される際に預けることになるので、家族が連絡したくても、携帯電話でやり取りすることはできません。
手紙は送れますが、勾留に接見禁止がつくと手紙のやり取りもできなくなる場合があります。また、手紙の内容はあらかじめ職員が精査するので、証拠隠滅のおそれがある場合などには、手紙の発受は認められなくなります。
被疑者と家族の連絡は大幅に制限されるため、すぐに連絡をとりたい場合は、弁護士に面会してもらうのがよいでしょう。
7、留置場には、女性専用の留置場がある
女性の特性に配慮した処遇をおこなうとの観点から、女性のみが留置される女性専用留置場があります。ただし、その数は令和5年4月1日時点で101施設と非常に少ないため、事件を起こした場所を管轄する警察署にはない場合が多くあります。
その場合は女性専用留置場がある警察署へ移送されるため、長距離の移動となることがあります。ひとつの場所に女性の被疑者が多く収容されていることから、弁護士の面会なども集中しやすく、家族が面会する際には、長時間待つこともあり得ます。
女性専用留置場は男性が留置された場所とは別の区画にあるため、同じ居室になることがなく、取り調べや運動などで居室の外に出るときにも、男性の被留置者と顔を合わせることがありません。
女性被留置者の身体検査や入浴の立ち会いは、必ず女性警察官や女性職員が担当します。男性が担当になることはないので、女性にとっては安心できる環境です。
留置場内では、化粧品や乳液などの基礎化粧品を自費で購入することや、洗面所でヘアブラシを使うことなどは認められています。
ただし、入浴は男性と同様に週1~2回で時間も20分程度、洗濯も週に1回程度です。
なお、女性の場合は衣服や下着の特性から、差し入れに制限がかかりやすくなります。
たとえばブラジャーや長い靴下などは、自殺防止の観点から禁止されています。差し入れをするときは男性の場合以上に確認が必要でしょう。
8、留置場から釈放されるために何ができる?
留置場に収容されてしまったら、釈放されるためにどのような行動が必要になるのでしょうか。
-
(1)勾留や延長の阻止
勾留は、定まった住所があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、検察官が勾留を請求せず、仮に請求しても裁判官が許可しません。
検察官や裁判官に対して逃亡や証拠隠滅のおそれがないと示すことで、勾留や勾留延長の回避が期待できます。
勾留が回避されると在宅捜査に切り替わり、身柄拘束による心身の負担を軽減できるでしょう。 -
(2)不起訴・略式罰金による終了
不起訴処分になると即日で留置場から釈放されるだけでなく、事件が終結し、前科もつきません。不起訴処分を獲得する方法は事件の内容によって変わりますが、たとえば反省文の提出や贖罪(しょくざい)寄付、依存症の場合は治療の準備といった活動が考えられるでしょう。
また100万円以下の罰金・科料に相当する軽微な事件では、被疑者の同意により略式起訴され、罰金・科料が言い渡される場合もあります。
この場合は不起訴と異なり前科がつきますが、罰金・科料の金額を納めて身柄を釈放されるため、事件によっては略式起訴を選ぶのもひとつの方法です。ただし、略式起訴は必ず前科がつくため、罪を犯していないにもかかわらず犯罪の疑いをかけられている場合や捜査機関からの指摘内容に反論などがある場合は、弁護士に相談し慎重に判断するようにしましょう。 -
(3)被害者との示談
被害者がいる事件では、示談の成立によって身柄釈放がはやまる可能性もあります。
- 被害者と接触して証拠隠滅を図るおそれがない(いわゆるお礼参りの危険性が低い)ため勾留を回避できる
- 深い反省がみられ、被害者も宥恕意思(ゆうじょいし・許すという意思)を示していることから、検察官が不起訴処分をくだす可能性が高まる
-
(4)保釈請求
起訴後も留置場に留め置かれた場合は、保釈を請求することができます。
保釈が認められると裁判までの間や裁判期間中は自宅で過ごせるため、弁護士との打ち合わせなど裁判の準備もしやすくなるでしょう。
保釈の請求は本人や家族でも法律上は可能ですが、保釈を許可すべき理由を具体的に示す必要があります。そのため、本人や家族による保釈請求を実際に認めてもらうのは困難なので、弁護士に任せるのが一般的です。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
9、留置場に収容されてしまったらすぐ弁護士へ相談を
家族が留置場に収容されてしまった後は、刑事手続きが粛々と進められます。起訴・不起訴の決定までに時間的な余裕がないため、早急に弁護士へ相談しましょう。
-
(1)弁護士なら速やかに面会や連絡が可能
逮捕後72時間以内は家族であっても面会が許されず、本人の様子を知ることや、励ましの言葉をかけてあげることはできません。事件によっては接見禁止がつき、勾留段階に入ってからも面会できない場合があります。
一方、弁護士は逮捕後の72時間以内や、接見禁止がついた際にも、制限なく本人と面会できます。
弁護士がはやい段階で面会すれば、取り調べで不利な供述調書をとられないためのアドバイスを与え、今後の見通しなども伝えられます。
このように弁護士は、家族との連絡の橋渡しにもなってくれるでしょう。 -
(2)釈放のための弁護活動
早期に身柄を釈放されるために、弁護士は検察官・裁判官に対し、「同居の家族の監督に期待できること」「すでに有力な証拠が確保されていること」など客観的な根拠資料を示しながら、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと主張します。
示談についても、犯罪の被害者は加害者やその家族との接触を嫌うケースが大半なので、弁護士が代理となり交渉を進めます。
弁護士が交渉することで、被害者の精神的な負担が減って示談に応じやすくなるほか、重要な条項(宥恕条項や被害届の取り下げ条項など)を不足なく盛り込むことができます。早期の身柄釈放や不起訴処分につながりやすくなるでしょう。
10、まとめ
逮捕され留置場に収容されると、釈放または起訴されるまでに、最長で23日もの間を過ごさなければなりません。
留置場は刑務所と異なり労役を課されることはないとはいえ、外部との連絡や生活に大きな制限がかかるため、少しでもはやい釈放を目指す必要があります。
しかし、留置場からの釈放につながる活動の多くは弁護士でなければできないものであり、家族だけで動いても思うような結果にならないことがほとんどです。前述のとおり、弁護士なら回数などに制限なく逮捕された本人と面会ができたり、被害者との示談交渉を適切かつ迅速に進めたりすることができます。
家族が留置場に収容された場合は、できるだけはやく弁護士にサポートを依頼するのが賢明です。刑事事件の経験が豊富なベリーベスト法律事務所が力を尽くします。ご家族だけで悩まず、まずはご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。