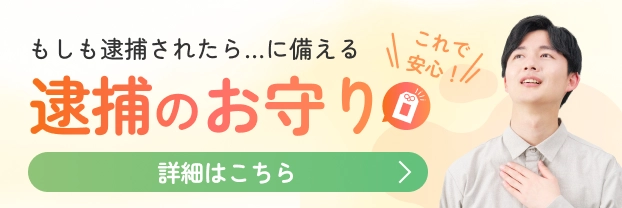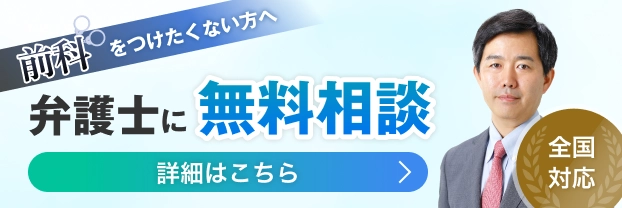- その他
- 未必の故意
未必の故意とは? 故意の判断基準やどのような状況で成立するかを解説


犯罪の成立要件として非常に重要な位置づけにあるのが「故意」です。故意が争点になっている、といった報道を耳にしたことがある方も多いでしょう。
平成30年12月に三重県で起きた交通死傷事故では、一般道を時速146キロメートルという高速度で走行させた行為に危険運転としての故意があったのかが争われました。報道によると、裁判所は「故意は認められない」と結論づけたものの、交通事故の裁判事例に詳しい専門家は「客観的に未必の故意が推認できる」とも指摘しています。
「故意」や「未必の故意」が認められるのかどうかは、犯罪の成立や刑罰の軽重を決定づける重要な問題です。本コラムでは、刑事事件における「故意」と「未必の故意」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、故意の種類
故意とは、一般的には「わざと」「意図的に」といった意味で解釈されますが、法律上の故意はさらに厳密な意味をもっています。
-
(1)「故意」とは? 故意と過失の違い
法律上の故意とは、自らの行為が他人の権利を侵害する結果になる、あるいは違法であると評価されるという結果を認識しながら、あえてその行為をすることと解釈されています。
単に自らの意思で行為に至ることでは足りず、権利を侵害する、あるいは違法な結果を自らが認識していないと故意は成立しません。
故意が成立しない行為は「過失」が成立します。過失とは、ある結果を認識・予見できていたにもかかわらず、必要な注意を怠って権利侵害や法益侵害を招くことです。
まったく同じ行為によって同じ結果が生じたとしても、故意であると認定された場合と、過失と判断された場合では、法律上の扱いに差が生じます。
刑法第38条1項は「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定め、特別の規定がない限り、故意が認められる場合のみを処罰し、過失であれば罰しないことを明示しているのです。
ここでいう「特別の規定」とは、過失による行為で結果が生じた場合でも処罰を下すことが明記されている犯罪を指しています。過失が条件となる犯罪としては、過失致死・過失傷害・失火などが代表的です。 -
(2)故意の種類は2つ
故意には「確定的故意」と「未必の故意」という2つの種類があります。
確定的故意とは、自らの行為によって、犯罪にあたる事実が発生すると確実に認識している状態を指します。一般的に通用している「わざと」「意図的」といったイメージは、確定的故意を意味していると考えられるでしょう。
一方、未必の故意とは、犯罪による結果の発生は確実ではないものの「結果が発生しても構わない」と認容している状態を指します。明確な故意をもっていなくても、意図的な犯罪であることと同等に評価されるため、未必の故意の認定は争点になりやすい問題です。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
2、未必の故意が成立するとどうなるのか
未必の故意の成立は、犯罪の成立に重大な影響を与えます。
たとえば、ナイフを使って人を刺したとしましょう。
手が滑ってしまい誤って刺した場合は「過失」となり、相手が負傷すれば過失傷害罪に、死亡させれば過失致死罪に問われます。
相手を故意に殺すつもりで刺す、あるいは死ぬかもしれないがそれでも構わないという「未必の故意」があれば殺人罪が成立しますが、脅すつもりでナイフを突きつけた結果、刺してしまったという殺意がない状況であれば、傷害罪や傷害致死罪が適用されるにとどまります。
「ナイフで人を刺して死傷させたと」いう行為と結果は同じでも、故意・未必の故意・過失の区別でこれだけのパターンが存在するわけです。
冒頭で挙げた交通死傷事故の事例でも、一般道で制限速度を大きく超えるスピードを出して走行する行為について、検察官は未必の故意を主張して危険運転致死傷罪の適用を求めていたとされています。
しかし裁判所は、わずかな操作ミスで事故を発生させる危険があったことは認めつつも、運転技術を過信していたに過ぎず故意を認めるには疑いが残るとして、過失運転致死傷罪を適用したのです。
自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)では、次のように規定しています。
被害者を死亡させると1年以上の有期懲役(最高20年)、負傷させると15年以下の懲役
●過失運転致死傷罪
7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
どちらが適用されるのかによって刑罰の軽重にこれだけの差が生じることから、故意が認定されるかどうかが重要な問題であることは明らかです。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、弁護士に相談できること
自分自身では悪意をもって実行したわけではない行為でも、行為の態様や状況などから未必の故意を疑われてしまうことがあります。未必の故意が認められてしまうと、同じ結果が生じた場合でもより重く処断されてしまう事態を招くので、故意ではないことを証明しなくてはなりません。
しかし、捜査機関の取り調べに対して「わざとではない」「こんな事態になるとは思っていなかった」と主張しても、簡単には納得してもらえないでしょう。
未必の故意がなかったことを証明するには、客観的な事実が必要です。
犯罪の容疑をかけられてしまい、未必の故意かが争点となっている場合は、直ちに弁護士に相談してサポートを求めましょう。取り調べにおいて適切な供述ができるようアドバイスをする、捜査機関に対して合理的な主張をするなどの弁護活動を行います。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
4、まとめ
わが国の処罰法令において処断されるのは、過失を処罰する規定が設けられている一部の犯罪を除き、原則として故意がある場合に限られます。また、故意または未必の故意が認定された場合には、同じ結果が生じたとしても、より重い刑罰が下されてしまうおそれがあります。過失にとどまるのか、故意・未必の故意が認められてしまうのかは重要な問題です。
悪意のない行為について犯罪の容疑をかけられてしまった場合は、直ちに弁護士に相談してください。故意・未必の故意・過失が争点となる刑事事件の弁護活動は、数多くの解決実績をもつベリーベスト法律事務所にお任せください。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。