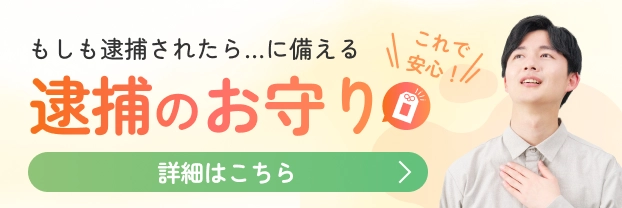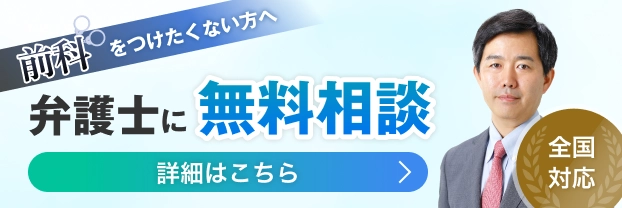- その他
- 釈放
逮捕後に釈放されるのはどのような場合? 釈放に向けた弁護士の役割


刑事事件を起こしてしまうと、逮捕や勾留などによって身柄を拘束される場合があります。身柄を拘束されると、会社や学校に通う、家族と一緒に過ごすといった自由な行動ができなくなるなど、実生活に影響が出てしまいます。
釈放されるタイミングはいくつもあり、状況によって求められる行動が変わってきます。刑事手続きには時間的な制約もあるため、適切なタイミングで釈放を目指すことが大切です。
本コラムでは、刑事事件で身柄拘束を受けた場合に釈放されるタイミングを整理した後、早期の釈放に向けて弁護士が担う役割について解説していきます。
1、逮捕後に検察官送致が行われずに釈放される場合
逮捕された被疑者は警察官による取り調べを受けて、逮捕から48時間以内に検察官に送致されることになります。
「送致」とは被疑者の身柄と事件資料を検察官に引き継ぐことをいい、刑事事件では、全件送致主義を原則としています。
しかし、刑事事件であっても、例外的に送致されない場合もあるのです。
-
(1)微罪処分になった場合
微罪処分とは、軽微な犯罪については検察官に送致せずに、警察のみで処理をすることを指します(刑事訴訟法第246条ただし書き)。
微罪処分として処理されると事件はそこで終了することになり、前科はつきません。
警察限りで処理するといっても、「どの事件を微罪処分とするのか」という運用が曖昧な場合には問題となります。そのため、運用の基準は、あらかじめ各地検の検事正によって定められています。したがって、ある事件が微罪処分となるかどうかには地域ごとに違いが生じるのですが、おおむね次のような基準にもとづいて判断されるのです。
- 被害が極めて軽微(被害額は概ね2万円までが目安)
- 犯情が軽微
- 被害回復がなされている
- 被害者の処罰感情が高くない
- 素行不良でなく偶発的
たとえば、口論が元で暴行をしてしまった場合、加害者が初めて起こした事件であり、なおかつ被害者のけがの程度が軽く、被害者が「自分も悪かった」と相手に対して罰を望んでいないような場合には、微罪処分として釈放される可能性があるのです。
-
(2)在宅事件として扱われた場合
「逮捕」とは、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがある場合になされる、身柄拘束の手続きとなります。逆にいえば、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には逮捕する必要がなくなるため、被疑者の身柄を在宅においたまま捜査が進められることになるのです。このような事件を、「在宅事件」といいます。
したがって、いったんは逮捕された場合でも逃亡や証拠隠滅のおそれがないと警察に判断された場合には、釈放されたうえで在宅事件に切り替えられる可能性があるのです。
ただし、在宅事件でも捜査は進められることになるので、検察官送致や起訴をされる可能性は残りつづけます。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
2、逮捕後に勾留されずに釈放される場合
警察官から送致を受けた検察官は、24時間以内に、起訴や釈放などの処分を決定します。
しかし、多くの場合に、逮捕直後の限られた時間内では捜査は尽くされていません。そのために、検察には「勾留請求」を行うことが認められているのです。
勾留請求が裁判所に認められた場合には、被疑者は原則として10日間、勾留の延長が認められた場合にはさらに10日間の身柄拘束を受ける可能性があります。ただし、勾留は長期間の身体拘束をともなう強力な手続きであるために、認定の可否には厳格な要件が定められているのです。
-
(1)勾留の要件
勾留は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があったうえで、次の要件を満たしている場合にのみ、認められます(刑事訴訟法第60条)。
- 定まった住所を有しないこと
- 証拠隠滅のおそれがあること
- 逃亡のおそれがあること
-
(2)勾留されずに釈放される場合
逮捕されたが勾留されずに釈放される場合のパターンとは、以下のようなものになります。
- 検察官が勾留請求しなかった場合
- 検察官が勾留請求したが、裁判官が勾留を認めなかった場合
また、裁判官が勾留を決定したが、弁護士の活動によって勾留が取り消されて、釈放される可能性もあります。具体例は、下記のような場合になります。
- 弁護士が勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行い、これが認められた場合
- 弁護士が勾留取消請求を行い、勾留が取り消された場合 など
勾留されずに釈放された場合は在宅事件に切り替わり、在宅のまま捜査が続けられることになります。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、略式起訴によって釈放される場合
検察官は、起訴について、最終的には「略式起訴」「公判請求」「不起訴処分」のいずれかの判断を下します。
このとき、「略式起訴」の判断がされた場合には、被疑者が釈放されることになります。
-
(1)略式起訴とは
略式起訴とは、公判を開かず書面審査によって刑を科す簡易な手続(略式手続)を求める、起訴手続きです。
公判請求は、最終的な判決が下るまでに数箇月、または数年を要する場合があります。しかし、社会のなかでは多くの事件が発生しているため、すべての事件で公判請求を採用していては裁判に人手や時間がかかりすることになってしまいます。したがって、比較的軽微な事件であり、本人の同意があるという条件付きで、迅速に処理するための簡易的な手続きである略式手続が実施されているのです。
-
(2)略式起訴の条件
以下の条件を満たした事件は、略式起訴の対象となります(刑事訴訟法第461条、461条の2)。
- 簡易裁判所の管轄事件であること
- 100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること
- 被疑者が同意していること
-
(3)略式起訴による釈放
略式起訴に同意すると、すぐに手続きが開始され、遅くとも14日以内に略式命令(判決)が下されることになります(刑事訴訟規則第290条1項)。
罰金・科料の告知があれば勾留の効力が失われるため、そのタイミングで身柄が釈放されます(刑事訴訟法第345条)。
警察官に徴収窓口を案内されて、言い渡された金額を納付することで、事件が終了します。本人が現金を持ち合わせていない場合には、家族に持参してきてもらうことになるでしょう。
-
(4)罰金の納付ができなかった場合
罰金・科料を納付できない場合には、納付書を受け取ったうえで後日に納めることになります。このとき、任意で期日までに支払わない場合には、財産に対する強制執行が行われます。強制執行する財産がない場合は、最終的には刑事施設内の「労役場」に留置されます。
労役場に留置された場合には、強制的に労働作業をさせられることになります。留置される日数は裁判で決定しますが、多くのケースでは1日の作業が5000円に換算され、罰金の額に到達するまで留置されます。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
4、不起訴になり釈放される場合
逮捕されたのちに釈放されるパターンのひとつが「不起訴処分」です。
不起訴処分は略式起訴と異なり前科が付かないため、事件の終わり方としては、被疑者やその家族にとって理想的なものであるといるでしょう。
-
(1)起訴と不起訴
起訴には略式起訴と公判請求があります。
略式起訴された場合には、罰金・科料を支払うことで事件は終了します。一方で、公判請求された場合には、刑事裁判が行われるのを待たなければいけません。
しかし、不起訴になった場合には、刑事裁判を受けたり刑を科されたりすることはなく、そのまま事件が終了します。不起訴になった時点で、すぐに身柄を釈放されて、自宅へ帰ることができるのです。
-
(2)不起訴になる場合とは
不起訴処分は、さまざまな理由から決定されます。
そのなかでも代表的な理由について紹介いたします。
● 嫌疑なし
犯人ではないことが明白なときや、犯罪の成否を認定する十分な証拠がないことが明白なときには「嫌疑なし」として不起訴処分になります。
典型的には、真犯人が見つかって疑いが完全に晴れた場合には「嫌疑なし」となります。
● 嫌疑不十分
犯人である疑いは残っているが、犯罪の成立を認定する証拠がないときには、「嫌疑不十分」として不起訴処分になります。証拠がなければ起訴しても有罪にできないため、検察官は不起訴にして釈放することを選択するのです。
● 起訴猶予
犯人であることが明白で、裁判で有罪になるだけの証拠がある場合であっても、被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の行動などのさまざまな事情や状況を考慮して、「起訴猶予」が決定されることがあります。
不起訴処分にいたる理由のなかでもとくに多いのが、「起訴猶予」です。罪を犯したのが事実であっても、事件の内容や事件後の行動次第では不起訴処分を得られる可能性があるという点は、被疑者にとっては重要です。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
5、保釈が認められて釈放される場合
不起訴処分のように完全な釈放とはいませんが、起訴後に限り、一時的に身柄を解放される「保釈」も釈放されるタイミングのひとつです。
-
(1)保釈とは
保釈とは、保釈金の納付を条件に、起訴後勾留を受けている被告人の身柄拘束を解く制度をいいます。保釈が認められると、釈放されて通常の生活を送り、裁判期日になると出頭して裁判を受けることになります。身柄拘束によって肉体的・精神的負担が軽減されるだけでなく、弁護士と裁判の打ち合わせを入念に行うことも可能になるのです。
裁判で実刑判決が言い渡されるとふたたび身柄を拘束されますが、執行猶予付き判決や罰金刑などが言い渡された場合は、社会生活を継続できます。
保釈の請求ができるタイミングは起訴された後であり、起訴前の逮捕・勾留段階では保釈が認められることはありません。
-
(2)保釈の条件
保釈は、起訴された被告人を一時的とはいえ釈放する制度であるため、請求が認められるためには条件があります。保釈には主に権利保釈と裁量保釈の2種類がありますが、それぞれの条件は下記の通りです。
● 権利保釈(刑事訴訟法第89条)
重大犯罪ではないこと、一定の前科や常習性がないこと、証拠隠滅や被害者へ危害を加えるおそれがないことなどを条件とした保釈。
● 裁量保釈(同第90条)
逃亡または証拠隠滅のおそれの程度、身体拘束により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上の不利益などを考慮し、裁判官の裁量で認められる保釈です。
-
(3)保釈から釈放までの流れ
保釈の請求後、保釈が認められると保釈金額が定められるため、その金額を裁判所の出納課へ納付することになります。保釈金は家族が用意して、弁護士が納付する場合が多いでしょう。その後、領収印を押された保釈許可決定書を弁護士が担当部署に提出して、1~2時間後には保釈されます。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
6、執行猶予によって釈放される場合
裁判が開始されたのちにも、釈放が行われるタイミングがあります。それは、執行猶予付き判決を受けた場合です。
-
(1)執行猶予とは
執行猶予とは、言い渡された刑の執行が一定期間だけ猶予され、猶予期間中に罪を犯さないことを条件に刑の効力が失われる制度です。猶予される期間は1~5年の間で裁判官が決定します。
たとえば「懲役1年、執行猶予3年」となった場合、本来であれば1年間の懲役刑を受けるところ、猶予期間である3年の間にふたたび罪を犯さなければ、懲役刑を受ける必要がなくなるのです。
ただし、執行猶予が付されても有罪判決であることに変わりはないため、前科はつきます。
裁判で執行猶予付きの判決が下されると勾留の効力が失われて、釈放されることになります(刑事訴訟法第345条)。所持品を取るためにいちど留置施設に戻る場合はありますが、ふたたび拘束を受けることはないのです。
-
(2)猶予期間中に刑事事件を起こした場合
猶予期間中に刑事事件を起こして、なおかつ禁錮以上の刑の有罪判決を受けてしまった場合には、執行猶予が取り消されることになります(刑法第26条第1号)。猶予期間中に起こした事件で罰金刑だった場合や、保護観察付きの猶予期間中には保護観察のルールに違反して、その情状が重い場合などにも執行猶予が取り消される可能性があります(刑法第26条の2第1号、2号)。
執行猶予が取り消されると、本来受けるべきであった刑を受けるのに加えて、新たに言い渡された刑も受けることになるのです。
たとえば「懲役1年、執行猶予3年」の判決の猶予期間中に「懲役3年」の実刑判決を受けた場合には、最初の事件の1年に加えて新たな事件の3年、合計4年間の懲役に服することになります。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
7、無罪判決によって釈放される場合
無罪の判決を言い渡された場合には、即日、身柄が釈放されます(刑事訴訟法第345条)。執行猶予付き判決と異なり、前科が付くこともありません。
-
(1)無罪判決の場合は刑事補償請求ができる
無罪判決が出たということは、無実の罪の責任を追及されて、逮捕や勾留をされていた場合には不当に身柄を拘束されていたということになります。そのため、国に対して一定の金銭補償を求めることができます。
補償には、大きく分けて刑事補償請求と費用補償請求の2種類があります。
● 刑事補償請求
刑事補償法にもとづき、身柄拘束されていた期間の損害に対する補償を請求するものです。金額は身柄拘束された1日あたり1000円から1万2500円の範囲内で決定します(同第4条第1項)。身柄拘束の損害に対する補償なので、在宅事件で逮捕も勾留もされなかった場合は対象外です。
● 費用補償請求
刑事訴訟法にもとづき、裁判に要した費用に対して補償を請求するものです(第188条の2)。補償の対象となる範囲は法律で定められています。具体的には、被告人や弁護士が裁判所へ出頭するための旅費、日当、宿泊費、弁護士報酬が該当します(刑事訴訟法第188条の6)。
-
(2)無罪判決後も勾留される場合がある?
無罪判決に対して検察官が控訴して勾留請求を行った場合には、無罪判決の後にもかかわらず勾留される場合があります。
このような事例は、被告人が在留資格のない外国人である場合に、多く見られます。退去強制により国外に出てしまうと、控訴審で有罪判決が出ても刑を執行することができなくなってしまうためです。
-
(3)有罪判決でも釈放される場合がある
判決で罰金または科料の「財産刑」を言い渡された場合には、勾留状が失効するため、釈放されることになります。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
8、釈放と仮釈放の違い
刑事裁判で実刑が確定して刑務所に収監された後にも、釈放されるタイミングがふたつあります。刑期を満了したときに身柄を解放される「釈放」と、刑期の途中で身柄を解放される「仮釈放」です。
-
(1)釈放と仮釈放の違い
「釈放」とは、身柄拘束から解かれることを幅広く指す言葉です。刑の満期にともない刑務所から出所することも、釈放にあたります。この場合は刑期を終えての釈放ですから、出所後の生活に関する制限はとくにありません。
一方で、「仮釈放」とは、懲役または禁錮の刑に処せられた者が刑期の途中で釈放される制度のことになります。あくまでも「仮」の釈放なので、仮釈放中に罪を犯して罰金刑以上の刑に処せられたときや遵守事項を守らなかったときには仮釈放が取り消されて、ふたたび刑務所に収監されることになります。
また、仮釈放中は保護観察に付されるため、保護司から面接や生活指導などを受けつつ、生活することになるのです。
-
(2)仮釈放が認められる場合とは
仮釈放の要件は、ふたつあります(刑法第28条)。
ひとつめの要件は、「改悛(かいしゅん)の状があること」です。改悛とは、自分の行を悔い改めて、心を入れ替えることです。すなわち、自らの犯した罪への後悔があり、改善更生の意欲が見られ、再犯の可能性が著しく低いなどの諸条件を満たした場合において、「保護観察による改善更生が妥当である」と判断されると仮釈放が認められるのです。
どのような場合に改悛の状が認められるのかは、「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」の第28条および通達によって、次のように定められています。
- 悔悟の情がある……受刑者の発言や文章のみで判断しない
- 改善更生の意欲がある……被害者に対する慰謝の措置の有無、刑事施設内での取り組みや生活態度などから判断する
- ふたたび犯罪をするおそれがない……受刑者の性格や年齢、釈放後の生活環境などから判断する
- 保護観察に付することが改善更生のために相当である……上記三つの条件を満たした者について総合的かつ最終的に相当であるかを判断する
- 社会感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りではない……被害者感情や収容期間などから判断する
ふたつめの要件は、有期刑については刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過していることです。ただし、実際に仮釈放されるのは、この期間が経過してからずっと後になることが大半です。
また、法律や規則には書かれていませんが、適切な身元引受人がいることも実質的に仮釈放の条件といます。安定した生活を送り、仮釈放後の生活を監督してもらうことは、更生のためには不可欠であると考えられているためです。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
9、早期釈放に向けた弁護士の役割
刑事事件で早期の釈放を実現させるためには、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士であれば、以下の活動を通じて、早期釈放の可能性を高めることができます。
-
(1)勾留を防ぐ
勾留されると最長で20日間と長期の身柄拘束を受けるため、日常生活に大きな影響が及ばされます。そのため、弁護士が検察官に対して、逃亡や証拠隠滅のおそれがない根拠を示して、勾留を請求しないように求めることになります。
検察官が勾留請求した場合でも、裁判官に対して請求の棄却を求めたり、勾留決定後も準抗告や勾留取り消しなどの活動をしたりすることによって早期の釈放を目指すことになるのです。
-
(2)保釈請求を行う
起訴された場合は弁護士が保釈を請求します。被告人や法定代理人、配偶者などでも保釈請求は可能ですが、保釈の条件を一般の方が判断するのは困難であり、請求方法を調べるのには時間がかかるでしょう。したがって、保釈を実現させるためには弁護士を通じて請求することをおすすめします。
-
(3)略式起訴を目指す
有罪判決が見込まれる場合には、略式起訴による釈放を目指すこともできます。略式起訴の場合、公判請求と異なり迅速に手続きが進むうえ、下される刑は罰金または科料です。懲役刑のように刑務所に収監されることがないため、早期に社会復帰しやすくなるのです。
ただし、略式起訴を受け入れると、「前科」が付くことになります。メリットとデメリットの両方を考慮して、弁護士と相談しながら慎重に判断を行う必要があるでしょう。
-
(4)示談を行う
被害者がいる事件の場合、被害者との示談を行うことで不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できたり、重すぎる刑を回避できたりする可能性が高まります。
しかし、刑事事件では、そもそも被害者の連絡先が分からない、連絡先が分かっても被害者の処罰感情が強くて示談を拒否される、といった状況になることが多々あります。
弁護士であれば、検察官を通じて連絡先を入手したうえで、被害者感情に配慮しながら慎重に交渉することができることもあります。したがって、被疑者の家族が示談を求める場合よりも、被害者に示談交渉に応じてもらえる可能性は高くなるでしょう。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
10、まとめ
刑事事件の被疑者となって逮捕された場合、逮捕段階や勾留段階、起訴後などのさまざまなタイミングで「釈放」が行われる可能性があります。早期に釈放されるためには、それぞれのタイミングに応じて適切な行動を起こすことが大切です。身柄拘束を受けている本人やご家族が的確に判断するのは難しいため、逮捕直後から弁護士に相談することが重要になります。
もしご自身やご家族が逮捕されたら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力を尽くしますので、まずはお問い合わせください。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。