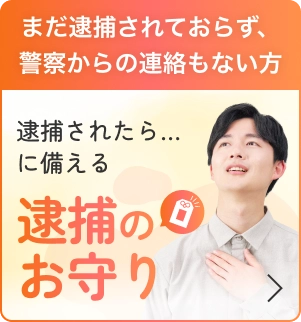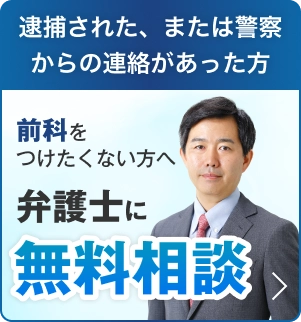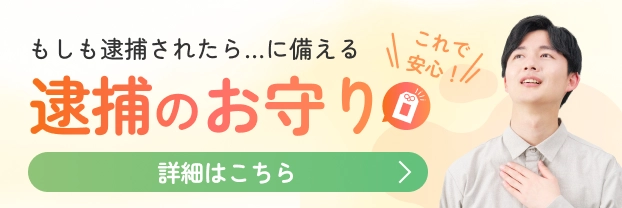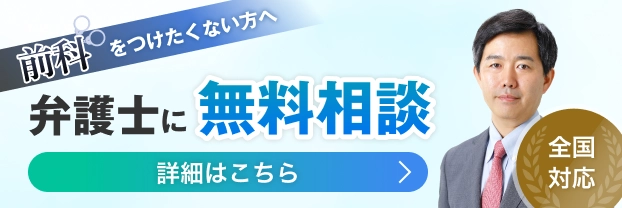- その他
- 黙秘権
黙秘権とは|行使すると不利になる? 黙秘するメリットとデメリット


黙秘権は、刑事事件において被疑者や被告人が自己に不利益な供述を強要されないための重要な権利です。しかし、黙秘権を行使することで罪が重くなるのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
最近では、黙秘権行使中に検察官から侮辱的な発言を繰り返されたとして、国に賠償を求めて訴訟を提起した事件がありました。令和6年7月18日の判決で検事の取り調べは違法だったと認められ、国に110万円の賠償が命じられました。このような事例からも、黙秘権の理解と適切な行使の重要性が問われています。
本コラムでは、黙秘権の概要や行使する際のメリット・デメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所 刑事事件専門チームの弁護士が解説します。
1、黙秘権の意味と法的背景
黙秘権とは、どのような意味なのでしょうか? 本章では、刑事事件の取り調べにおいて重要な黙秘権の定義とその法的背景について解説していきます。
-
(1)黙秘権の定義
黙秘権とは、刑事手続の中でいえば、罪を犯した嫌疑を受けている被疑者や被告人が、警察や検察の取り調べや裁判所の尋問において供述を拒否できる権利を指します。
日本国憲法38条1項には、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と明記されています。また、刑事訴訟法311条1項にも「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」と規定がされています。
以上のことから、黙秘権は憲法や法律で保障された権利であるため、黙秘権の行使を理由に不利益を被ることは原則としてありません。 -
(2)なぜ憲法や法律で保障されているのか
黙秘権が憲法や法律で保障されている理由は、被疑者や被告人の人権と利益を守るためです。
歴史的に、犯罪の嫌疑がある者に対しては、拷問などを用いて自白を獲得しようとされていました。黙秘権が認められない場合、不当な取り調べや尋問によって自己の意思に反した自白を強要されかねません。
上記のような自白強要の弊害の歴史から、国家が刑罰権を科すための手続きである刑事手続きにおいては、基本的人権として、自らが罪を負う可能性がある証言を強要されない権利として、黙秘権が確立しているのです。 -
(3)黙秘権を行使できないときがある
黙秘権は原則としてすべての被疑者・被告人に保障されていますが、例外的に行使できないときがあります。たとえば、以下のようなケースです。
- 氏名や住所を問われたとき
- 指紋や足形の採取や身体検査を行うとき(刑事訴訟法第218条)
- 酒気帯びの疑いで呼気検査を行うとき(道路交通法第67条)
黙秘権は、基本的に「自己に不利益な供述」を強要されないための権利です。氏名や住所に関しては答えたからといって刑事責任を負わされるものではないため、黙秘権の対象にはならないと考えられます。また、黙秘権は供述を拒否する権利ですので、供述以外の証拠を採取する行為も黙秘権の対象外となります。
2、黙秘権を行使する具体的な方法
前述のとおり、黙秘権は憲法や法律で保障された権利です。しかし、具体的な行使方法を知らない方が多いでしょう。誤った方法で行使するとかえって不利になる可能性もあるため、適切な対応を知っておくことが重要です。
以下では、黙秘権の具体的な行使方法について解説していきます。
-
(1)完全黙秘か一部黙秘を選べる
黙秘権を行使する場合、「完全黙秘」と「一部黙秘」のふたつの方法から選択できます。
完全黙秘とは、あらゆる質問に対して一切答えないことです。事件の詳細はもちろん、ささいなことであっても黙秘を貫きます。
一方で一部黙秘とは、供述する内容を選び、特定の質問にのみ答える方法です。たとえば、事件に関係のない情報は話すものの、事件の詳細については黙秘するなどの対応を指します。
どちらの方法を選ぶかは、被疑者・被告人の権利であるため、本人が自由に決められます。ただし、供述の影響を十分に考慮し、慎重に判断する必要があるでしょう。 -
(2)黙秘権を行使する方法
黙秘権を行使する際には、まず黙秘するかどうかを慎重に検討しましょう。自分にとって有利な供述ができる場面であれば話す選択肢があります。しかし、捜査状況がわからない段階では不用意な発言は避けるべきです。
実際に黙秘権を行使する際は、「黙秘します」と明確に宣言するだけでなく、なにも言わず沈黙を貫くことも認められています。逮捕前の取り調べや裁判に出廷したときなど、刑事事件手続きのどの段階であっても行使可能です。
ただし、黙秘権を行使すべきかの判断やタイミングについては、早めに弁護士へ相談しアドバイスを受けることをおすすめします。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、黙秘権の行使で得られるメリット
黙秘権の行使は、被疑者や被告人が自らの権利を守るための有効な手段です。黙秘権の行使で得られる具体的なメリットについて解説します。
-
(1)証拠となる「自白供述」をとらせない
黙秘権を行使することで、不利益な証拠となりうる「自白供述」をとらせないメリットがあります。
刑事事件において、自白は有力な証拠のひとつとなりえます。しかし、取り調べでは、長時間にわたる圧力や巧妙な誘導によって、事実とは異なる発言をしてしまうケースが起こりえます。しかし、そのような発言は、自白供述として決定的な証拠とされてしまい、判決に影響を与えてしまうのです。
黙秘権を行使することで、不確かな記憶で誤って自ら犯罪を認めるような供述をしてしまう可能性をつぶすことができます。 -
(2)不用意な発言がもたらすリスクを回避する
自ら犯行を認める発言ではなくても、不用意に発言してしまった言葉がもたらすリスクを回避する点も、黙秘権を行使するメリットのひとつです。
供述の内容によっては、過剰に重い罪に問われてしまう要素のひとつとして扱われてしまうおそれがあります。たとえば、取り調べによる供述が原因で、本当はそうではないのに計画性があったなどと判断されてしまうと、科される罪が重くなってしまう可能性もあるでしょう。
黙秘を貫けば、不用意な発言をしてしまうこともありません。 -
(3)不要な誤解を受ける余地を作らない
黙秘権の行使には、不要な誤解を受ける余地を作らないメリットもあります。取り調べでは供述が記録され、裁判でも重要な判断材料となります。
しかし、供述内容が捜査官によって都合よく解釈され、意図しない形で証拠として扱われる可能性もあるでしょう。たとえば、話の前後の文脈が切り取られ、一部分だけが強調されることで誤解を招くケースなどが考えられます。
黙秘権を行使すれば、誤解や偏った解釈が生じるリスクを回避できます。 -
(4)信ぴょう性が疑われる要素を減らせる
黙秘権の行使によって、供述の信ぴょう性(信用性)が疑われる要素を減らせます。供述が二転三転すると、裁判において供述の「信ぴょう性(信用性)が低い」と判断される可能性があります。
取り調べの初期段階では精神的に動揺していることが多く、矛盾した内容を話してしまうケースもあるでしょう。しかし、一度供述した内容を後で覆しても、「不自然な供述変更」と捉えられ、不利な扱いを受ける場合があります。
初期の取り調べでは、十分に状況を理解するまで黙秘を続けることで、後の証言の一貫性を保てるでしょう。
4、黙秘権を行使したとき受けうるデメリット
黙秘権は法律で認められた正当な権利ですが、行使することでデメリットをともなう可能性もあります。黙秘権の行使によってどのようなデメリットがあるのか、以下で具体的にみていきましょう。
-
(1)黙秘の有無だけで判決の内容は左右されない
裁判では「黙秘しているから有罪」とは判断されず、検察側が証拠によって立証しなければならないという原則が適用されます。
そのため、黙秘権を行使したことによって有罪かどうかが決まることはありません。
しかし黙秘によって、謝罪や反省の意思がみられないと推認される可能性はあるため、罪の重さに影響を与える可能性はあります。必ずしも黙秘が最善の選択になるとは限らない点に注意が必要です。 -
(2)身柄の拘束を受けやすい
身柄の拘束を受けやすいのは、黙秘権を行使するデメリットのひとつです。
刑事事件における逮捕の必要性は、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかによって判断されます。そのため、証拠隠滅や逃亡のおそれがなければ、身柄を拘束せずに捜査を進める在宅事件として処理されるケースもあります。
しかし、黙秘権の行使によって証拠隠滅や逃亡を疑われた場合は、身柄を拘束される可能性が高くなるでしょう。 -
(3)取り調べが長期化しやすい
黙秘を続けると、取り調べが長期化しやすいデメリットがあります。供述を引き出すために別の切り口から質問を繰り返したり、何度も取り調べを行ったりする可能性が高くなるためです。
取り調べの際には心理的圧力がかかりやすく、長時間取り調べが続くと精神的・肉体的に疲弊してしまう可能性があります。
捜査官はさまざまな方法で話を引き出そうとするため、長期の取り調べに耐えられるかどうかも考慮する必要があるでしょう。 -
(4)被害者からは反省していないと受け止められやすい
被害者がいる事件では、黙秘を続けることで「反省していない」と受け止められやすくなります。特に傷害事件や詐欺事件などでは、被害者側の処罰感情が強まり、示談交渉が難しくなるケースもあるでしょう。
裁判においても被害者の感情が考慮され、罪の重さに影響する可能性があるため注意が必要です。
事件の内容によっては、黙秘するよりも適切な供述を行う方が望ましい場合もあります。
5、黙秘権を行使すべきかどうかの判断基準
黙秘権を行使すべきかどうかは、事件の状況や供述の影響を考慮しながら適切に選択する必要があります。判断基準の参考として、黙秘を検討すべきケースと黙秘しない方がよいケースを解説していきます。
-
(1)黙秘を検討すべき代表的なケース
黙秘権の行使を検討すべき代表的なケースは、以下のとおりです。
- 犯行を否認する場合
- 自白を強要されるリスクがある場合
また、犯行を否認する場合、やっていないことを立証するのは非常に困難です。自白が強要されるリスクもあるため、黙秘の行使を検討すべきといえます。
-
(2)黙秘しない方がいいケース
黙秘権を行使しない方がいいケースとして挙げられるのは、以下のような状況です。
- 供述以外の証拠がそろっている場合
- 早期釈放を目指す場合
一方で、供述以外の客観的証拠があり、犯罪行為をしたことが明らかである場合も罪を認めた方がいい場合があります。黙秘権の行使によって心証が悪化し、処罰に影響する可能性があるためです。
また、黙秘は長期間の身柄拘束につながるおそれがあるため、早期釈放を目指す際には、黙秘権の行使を避けるべき場合もあります。 -
(3)自己判断せず弁護士に相談して検討を
黙秘権を行使すべきかどうかは自己判断せず、弁護士に相談して検討することをおすすめします。
刑事事件において黙秘権を行使するかどうかは非常に重要な決断であり、慎重な判断が求められます。しかし、自分にとって最適な対応を即座に判断することは困難です。
弁護士は、事件の内容や証拠の状況を総合的に判断し、どのように対応すべきかアドバイスができます。供述した内容は後から撤回することが難しいため、早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。
6、まとめ
黙秘権は、刑事手続きにおいて被疑者・被告人が自身を守るために認められている重要な権利です。しかし、その行使には慎重な判断が求められ、状況によっては有利にも不利にもなりえます。
取り調べにおいては、自分の発言がどのように扱われるかを十分に理解し、軽率な供述を避けることが大切です。黙秘するかどうかを判断する際には、取り調べの圧力に流されることなく、弁護士の助言を受けることが最善策となります。
ベリーベスト法律事務所の弁護士は、黙秘権行使の判断や適切なタイミングについてアドバイスができます。弁護人として弁護活動を行うことも可能なため、黙秘権の行使について疑問や不安がある方は当事務所へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。