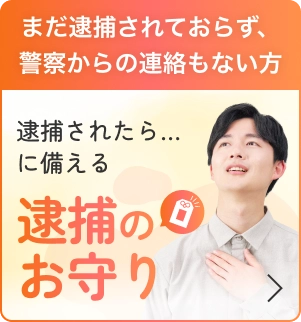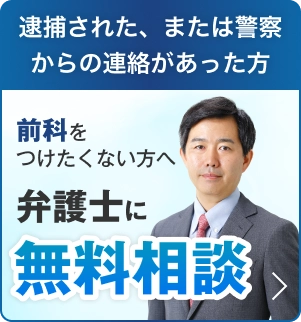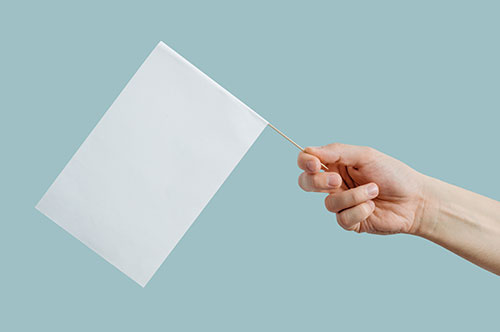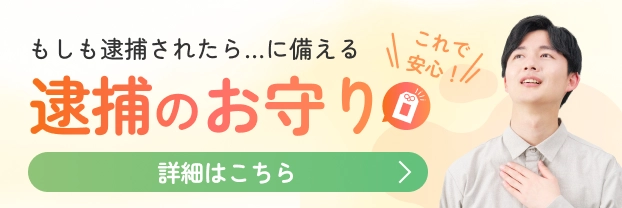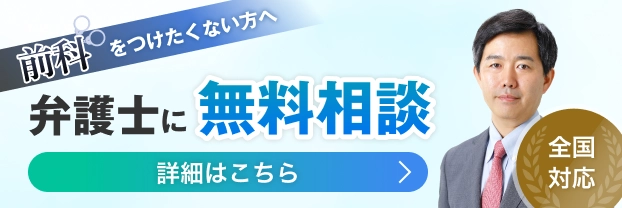- その他
- 国選弁護人
国選弁護人とは? メリット・デメリットと私選弁護人との違いを解説


ご自身やご家族が突然刑事事件で逮捕されてしまった際、弁護士に依頼すべきかどうか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような場合に選択肢のひとつとなるのが、「国選弁護人(こくせんべんごにん)」の選任です。
国選弁護人制度は、国の費用負担で弁護士をつけられる制度です。この制度を利用することで、経済的に余裕がない場合にも弁護士のサポートを受けられます。
ただし、国選弁護人を選任するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。国選弁護人の選任を希望する際には、制度の特徴や自費で依頼する「私選弁護人」との違いを正しく理解しておくことが大切です。
本コラムでは、国選弁護人の選任条件や依頼方法・メリットデメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、国選弁護人制度とは? どういう制度?
そもそも国選弁護人制度とは、具体的にどのような制度なのでしょうか?
まずは、制度の内容や対象となる犯罪、依頼にどの程度の費用が必要なのかなどの基本を確認していきましょう。
国選弁護人制度とは、経済的な事情などから弁護士を依頼できない場合に、国が費用を負担して弁護士を選任する制度です。刑事事件で勾留された被疑者や起訴された被告人は、国選弁護人制度を利用できる可能性があります。
- 被疑者や被告人の権利を守り支援すること
- 必要に応じて法的手続きや弁護活動を行うこと
- 捜査や裁判での不当な扱いを防ぐこと
弁護士がつくことで、法律の専門的な知識がない人でも、正当な手続きを経て自分の主張を伝えることができます。
2、国選弁護人制度の詳細と対象となるケース
国選弁護人制度は、「被疑者国選弁護制度」と「被告人国選弁護制度」に分けられます。
-
(1)被疑者国選弁護制度
対象となるのは、刑事事件で逮捕され、勾留された被疑者です。
- 勾留:勾留とは被疑者の逃亡や証拠の隠滅を防ぐために、警察署などの留置施設に留置して身柄を拘束する手続きです。
- 被疑者:「被疑者」とは、犯罪の嫌疑をかけられて捜査を受けている段階の人を指し、まだ起訴されていない状態です。
以前は起訴された被告人のみが対象でしたが、平成18年10月に被疑者国選弁護制度が施行され、被疑者も対象になりました。
また、施行当時は一定の犯罪のみに限られていましたが、平成30年6月以降、対象事件は被疑者が勾留されているすべての事件に拡大されています。
したがって、どのような犯罪の嫌疑であっても、刑事事件で勾留された被疑者であれば国選弁護人制度の利用できます。 -
(2)被告人国選弁護制度
対象となるのは、刑事事件で起訴され刑事裁判を受ける立場になった被告人です。
起訴されると、被告人国選弁護人を選任することができるようになります。
なお、国選弁護人は刑事手続きのための制度であるため、民事事件では選任できません。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、国選弁護人の依頼にかかる費用
原則として、国選弁護人を利用する際の費用は国が負担します。
そのため、依頼者である被疑者や被告人が弁護士費用を支払う必要はありません。
ただし、次のようなケースでは、刑事裁判の判決で裁判官から弁護士費用の負担を命じられる可能性があります。
- 経済状況の調査により、弁護士費用を支払える資産や収入があると認められた場合
- 将来的に就労などによって、費用を支払う能力があると見込まれる場合
国選弁護人の費用負担については、最終的に裁判官が被疑者または被告人の具体的な事情を考慮して判断します。
そのため、後から支払いを命じられる可能性があるということを、覚えておいたほうが良いでしょう。
4、国選弁護人を選任できる条件
国選弁護人は誰でも選任できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
しかし、条件を満たさない場合でも弁護士から支援を受けることは可能です。
国選弁護人の選任に必要な条件と、該当しない場合の対処法について解説します。
-
(1)必要な条件は4つ
被疑者または被告人が、国選弁護人の選任を裁判所に請求するために求められるのは、次のような条件です。
- 刑事事件で勾留されている被疑者、または起訴された被告人
- 被疑者または被告人本人が、国選弁護人の選任を裁判所に請求していること
- 弁護人が選任されていないこと
- 原則として資力が50万円未満であること
「資力」とは、被疑者や被告人が保有している現金や預金など(流動資産)の合計金額です。国選弁護人の選任を請求するには、これらの合計金額が50万円未満であることが、原則としての条件となります。
ただし、資力が50万円以上ある場合でも、弁護士会に私選弁護人の選任を申し出たにもかかわらず選任されていない状況であれば、国選弁護人の請求が認められることがあります。 -
(2)条件を満たさない場合は弁護士を選任できない?
国選弁護人を選任できる条件を満たしていない場合でも、弁護士からの支援を受ける方法はあります。代表的な方法は次の2つです。
- 当番弁護士制度を利用する
- 私選弁護人を選任する
- 当番弁護士制度:「当番弁護士制度」とは、逮捕・勾留されている被疑者や、その家族などの接見依頼によって、弁護士会が弁護士を1回に限り派遣する制度です。初回の接見については弁護士会が費用を負担してくれるため、依頼者側に支払いは生じません。
- 当番弁護士:当番弁護士は1回限りとなるため、継続的な対応を希望する場合や、特定の弁護士に依頼したい場合には「私選弁護人」を選任することになります。
- 私選弁護人:私選弁護人とは、被疑者自身または家族などが自由に選んで契約する弁護士のことです。弁護士費用は原則として自己負担になりますが、専門性や経験、実績などを重視して依頼できるほか、より柔軟で迅速な対応を受けられる可能性に期待できます。
5、状況別、国選弁護人が選任される流れ
国選弁護人がどのような手続きで選任されるのか、主に3つの典型的な場面に分けて解説します。
-
(1)勾留が決定したとき
刑事事件の被疑者として勾留が決定すると、被疑者国選弁護人の選任が可能になります。
被疑者として国選弁護人を選任する一般的な流れは次のとおりです。
- ① 留置施設にいる警察官などに、国選弁護人の選任を希望する旨を伝える
- ② 用意された書類に必要事項を記入し提出する
- ③ 裁判所が選任要件を満たしているかを審査する
- ④ 法テラスが、契約している弁護士より候補を指名する
- ⑤ 裁判所が正式に国選弁護人を選任する
-
(2)起訴されたとき
起訴され刑事裁判を受けることになった被告人に弁護人がついていない場合、身柄拘束中か在宅かにかかわらず、被告人国選弁護人を選任することができます。
- 身柄を拘束されたまま起訴された場合:身柄を拘束されたまま起訴された場合は、勾留中の施設(警察署や拘置所など)で、弁護人選任の意向を確認する書類が本人に交付されます。国選弁護人の選任を希望する場合は、必要事項を記入して提出します。
- 在宅で起訴された場合:在宅で起訴されたケースでは、裁判所から被告人の自宅に起訴状が送付されます。起訴状には「弁護人選任に関する回答書」が同封されるので、選任を希望する場合は、必要事項を記入して提出しましょう。
書類提出以降の国選弁護人を選任する流れは、被疑者国選弁護人と同様です。
なお、すでに被疑者国選弁護人を選任している場合は、原則として同じ弁護士が引き続き被告人国選弁護人となるため、新たに請求する必要はありません。 -
(3)即決裁判手続がとられたとき
起訴後に「即決裁判手続」がとられた場合には、被告人が希望の有無にかかわらず、裁判所が職権で国選弁護人を選任します。
即決裁判手続とは、証拠が明白で事実関係に争いがない軽微な事件について、迅速に審理と判決を終えることを目的とした簡易的な裁判手続きです。
基本的に1回の期日で審理は完結し、即日判決が言い渡されます。
即決裁判手続を行うためには、被告人の同意と弁護人の選任が必要です。
- 弁護人がいない場合:弁護人がいない場合には、刑事訴訟法第350条の18に基づき、裁判所は職権で弁護人を選任しなければなりません。
6、国選弁護人を選任するときの注意点
国選弁護人は、すべての事件において自動的に選任されるわけではありません。
利用を希望する場合は、自ら手続きを行う必要があります。
ここで重要なのが「自ら手続きを行う」ということです。原則として、本人の申請がなければ、国選弁護人は選任されません。
本人の申請が必要ということは、家族はサポートできないのか?
家族がまったく関与できないわけではなく、接見依頼や情報提供などを通じて、間接的に弁護士選任をサポートすることは可能です。
この章では、国選弁護人を依頼する方法や、家族ができる支援の内容について具体的に解説していきます。
-
(1)本人から依頼する
国選弁護人を選任する方法には、被疑者・被告人本人が請求する方法と、裁判所が職権で選任する方法の2通りがあることは前述したとおりです。
被疑者・被告人自身で請求する場合は、勾留または起訴の段階で、警察官や刑事施設の職員に「国選弁護人を選任してほしい」と伝えてください。
このとき重要なのは、本人の明確な意思表示が必要であるという点です。 -
(2)弁護人の選任について家族ができること
被疑者や被告人の家族は、国選弁護人を直接依頼することはできません。
しかし、次のような方法で間接的に弁護人の選任をサポートすることは可能です。
- 本人に国選弁護人を希望するように伝える
- 国選弁護人が選任されているか確認する
- 当番弁護士を利用する
- 私選弁護人を検討する
まずは面会や手紙などを通じて、本人に国選弁護人の依頼を促し、その後弁護人が選任されたかどうかを確認しましょう。
選任されていない場合や、制度上選任できない段階である場合には、当番弁護士や私選弁護人への依頼を検討することができます。
当番弁護士については、家族が弁護士会に連絡することで派遣を依頼できます。
また、私選弁護人も、家族が直接相談したり、接見を依頼したりすることが可能です。
これらの方法を状況に応じて検討しましょう。
7、国選弁護人のメリットデメリット
国選弁護人制度を利用するかどうかを判断するには、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが大切です。
-
(1)メリット
国選弁護人を選任する場合には、次のようなメリットがあります。
- 弁護士費用がかからない
- 自分で弁護士を探す必要がない
- 基本的な法的支援を受けられる
国選弁護人制度は、弁護士費用の負担が困難な方を対象とした制度であり、無料で弁護活動を受けられるのが最大の特徴です。
また、自分で弁護士を探す必要がなく、選任の手続きは比較的簡単なため、短期間でサポートを受けられるのも利点といえるでしょう。
刑事手続きの流れや取り調べの対応などについて弁護士からの助言を受けることができれば、精神的な不安や混乱の軽減にもつながります。 -
(2)デメリット
一方で、国選弁護人には次のようなデメリットもあります。
- 自由に弁護人を選任、解任できない
- 刑事事件の弁護経験が豊富にあるとは限らない
- 示談交渉が円滑に進まないおそれがある
国選弁護人は、法テラスによって指名された候補者の中から、裁判所が弁護人を選任する仕組みです。そのため、自分で弁護人を選んだり、解任したりすることはできません。
結果として、相性が合わないと感じたり、刑事事件の弁護経験が乏しい弁護士が選任されたりすることもあり得ます。
特に、被害者との示談交渉など積極的な対応や迅速な判断が求められる場面では、私選弁護人と比べて対応が遅れることも考えられるでしょう。
柔軟かつ積極的な弁護活動を希望する場合は、私選弁護人を検討したほうが良いケースもあります。
8、国選弁護人と私選弁護人のどちらが良い? 判断基準・ケース別の選任方法
弁護士を選ぶにあたって、国選弁護人と私選弁護人のどちらが適しているのか迷う方は少なくありません。
判断に迷ったときは、求める対応、費用面などを踏まえて検討することが重要です。
ここからは、判断の目安となるポイントや、具体的な選び方の考え方をご紹介します。
-
(1)判断基準のポイント
国選弁護人と私選弁護人のどちらを選ぶべきなのかは、「何を重視するか」で大きく異なります。選択の際は、次のような基準を参考にすると良いでしょう。
重視したい点 適している弁護人 費用を抑えたい 国選弁護人 迅速な対応を求めたい 私選弁護人 特定の弁護士に依頼したい 私選弁護人 早期の釈放を目指したい 私選弁護人
- 費用面を重視の場合:費用面での負担をできるだけ抑えたい場合には、国が費用を負担してくれる国選弁護人が適しています。ただし、選任できるタイミングまでに時間がかかる点や、弁護士を自由に選べない点には注意が必要です。
- 対応が早く、経験豊富な弁護士が良い場合:迅速な対応を希望する場合や、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼したい場合には、私選弁護人が適しているケースが多くなるでしょう。
特に、早期釈放を目指す場面では、迅速かつ柔軟に対応できる私選弁護人のほうが有利に働くこともあります。
ベリーベスト法律事務所の弁護士費用は、こちらからご覧ください。 -
(2)逮捕直後に弁護士に相談する重要性
刑事事件では、逮捕された直後の対応が、その後の流れに大きな影響を与える可能性があります。
できるだけ早い段階で弁護士に相談すれば、警察や検察への対応について適切なアドバイスを受けることが可能です。
また、被害者との示談交渉を早期に開始できれば、不起訴の獲得や釈放につながる可能性も高まります。
国選弁護人は原則として、勾留が決定してからでなければ選任はできません。
そのため、勾留される前の段階で相談したい場合は、まずは当番弁護士を利用しつつ、継続的な弁護を求める場合は、早めに私選弁護人の選任を検討しておくと安心です。
9、私選弁護人に依頼する方法
-
(1)弁護人の探し方
私選弁護人を検討する際は、信頼できる弁護士を見つけることが大切です。
しかし、そもそもどうやって弁護士を探せばいいのか分からない、と迷われる方は少なくありません。
まず、私選弁護人を探す基本的な方法として、次のようなものが挙げられます。
- インターネットで検索する
- 弁護士が登録しているポータルサイトで探す
- 知人から紹介してもらう
- 日本弁護士連合会(弁護士会)の相談窓口を利用する
もっとも手軽な方法は、インターネットを活用して情報を集める方法です。
たとえば、「東京 弁護士」のように地名+弁護士で検索する方法や、「刑事事件 弁護士」など、相談内容+弁護士で検索する方法があります。
各事務所のホームページには、在籍している弁護士のプロフィールだけではなく、対応している事件や過去の実績、費用の目安などの情報が掲載されていることが一般的です。
いくつかの事務所を比較しながら、検討することができます。
「話を聞いてみたい」と思う事務所が決まったら、電話やメールなどで、問い合わせをしてみてください。その後の流れについては事務所ごとで異なりますが、状況に応じて、わかりやすく案内してくれるでしょう。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただく場合のご相談の流れは、こちらで解説しています。 -
(2)ベリーベスト法律事務所へご相談いただくメリット
刑事事件で私選弁護人をお探しの方は、ベリーベスト法律事務所への相談も、ぜひご検討ください。
当事務所には刑事チームが組織されており、刑事事件の対応実績が豊富な弁護士がノウハウを共有しています。
ご状況を丁寧に伺い最善の解決策をご提案いたしますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。