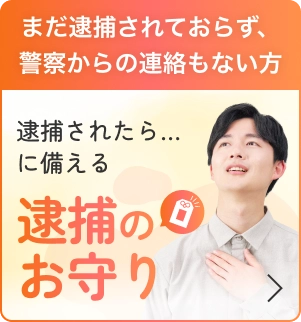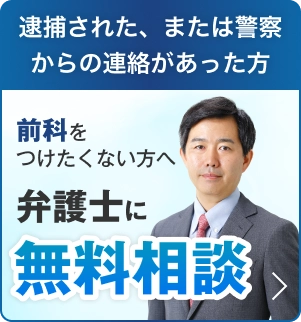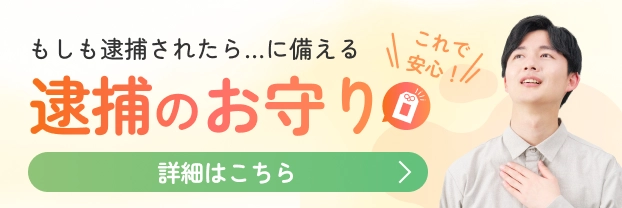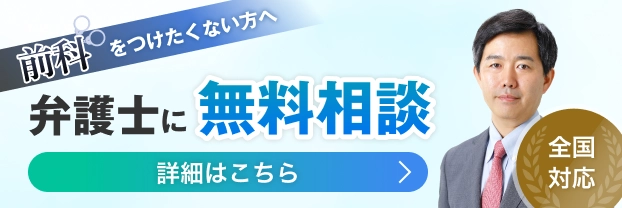- その他
- 自首
自首すれば罪は軽くなる? 刑が減軽されやすいケース・されにくいケース
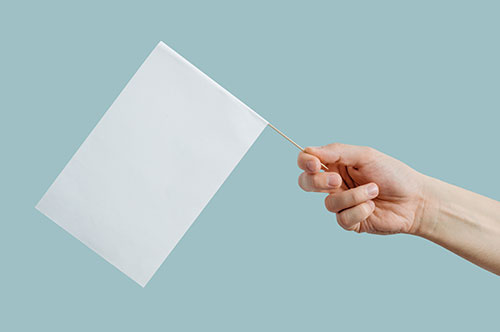
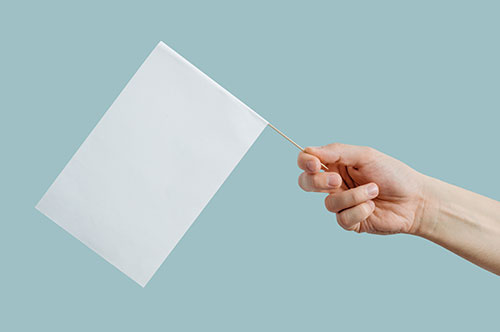
罪を犯してしまい、どうするべきか悩んでいる方の中には、「自首をしたほうがいいのかどうか」で迷っている方も多いのではないでしょうか。自首をすれば刑が軽くなると聞いたことがあっても、実際には「どのタイミングで?」「本当に刑が減軽されるのか?」といった疑問が尽きません。
結論からいえば、自首には刑を軽くする効果が法律で認められており、一定の条件を満たせば、逮捕の回避や不起訴となる可能性があります。ただし、自首が成立するためにはいくつかの条件があり、タイミングや方法によっては「自首が認められない」ケースもあるため注意が必要です。
本コラムでは、自首による刑の減軽の程度や条件、自首の手続きの流れ、自首の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事で分かること
- 自首が成立するための条件と注意点
- 自首することでどのくらい刑が減軽されるか
- 自首で刑が減軽されるケースとされにくいケース
1、自首とは? 出頭とどう違う?
まずは、「自首」とは法律上でどのような行為を指すのかを解説します。
-
(1)自主とは
自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に警察署などに出向くなどし、自分が罪を犯したことを申し出ることをいいます。
自首が認められると、法律上「刑を軽くできる」とされていて(刑法第42条)、状況によっては裁判で有利に働くこともあります。 -
(2)自首と出頭の違い
自分から警察に行くという点では「自首」と「出頭」はよく似ていますが、法律上はまったく違うものです。
出頭しても自首が成立しないケースもあるため、違いをきちんと理解しておくことが大切です。
① 出頭とは?
出頭とは、法律上厳密な定義はありませんが、すでに警察や検察から「この人が犯人の可能性がある」と見られている人(被疑者)が、自分の意思で捜査機関に出向くことをいう場合が多いです。自分で出向く場合と、出頭要請を受けて出向く場合があります。
② 自首と出頭の違い
出頭は、すでに捜査の対象となっている人が対象であるため、「自発的に罪を明らかにしてくれた」という法律上の評価にはつながりません。
つまり、自首と違って刑を軽くする効果(減軽事由)にはつながらないのです。
とはいえ、出頭したことが「逃げ隠れせず誠実に対応している」と評価され、最終的な処分や量刑において考慮されるケースもあります。
ただし、「自首したつもり」でも、実際には要件を満たしておらず、自首とみなされないこともあります。
正しく自首を成立させるには、知っておくべきポイントがあるのです。
2、自首が成立するための4つの要件
自首が成立するには以下の要件をすべて満たす必要があります。
法律で求められている「自首の4つの要件」について説明します。
-
(1)自発的に犯罪事実を申告すること
犯人自らが進んで犯罪事実を申告する必要があります。
たとえば、すでに犯罪を疑われており、取り調べを受けている中で罪を認めても、自首は成立しません。 -
(2)捜査機関に申告すること
自首する相手は、警察や検察などの捜査機関に限られます。
一般的には警察官への申告が多いですが、法律上は「検察官または司法警察員」とされています(刑事訴訟法第243条、241条1項)。
なお、司法警察員は、警察官の中でも巡査部長以上の階級にある人のことを指すため、たとえば交番の巡査に伝えただけでは、その時点では法律上の自首には該当しません。
もっとも、司法巡査が自首を受けた場合は巡査部長以上に取り次ぐ義務があるため(犯罪捜査規範第63条2項)、取り次がれた時点で自首が成立します。
そのため近くの警察署や交番に申告するという方法でも基本的に問題はありません。 -
(3)捜査機関に犯罪が発覚する前の申告であること
捜査機関に犯罪事実が発覚していない段階や、犯罪事実は発覚しているが犯人が誰であるかは、発覚していない段階で申告する必要があります。
犯罪の被害者や目撃者などが犯人だと把握していても、警察官や検察官などの捜査機関が把握していなければ、発覚前と判断され自首が成立します。
発覚前とは言えないケース
一方で、犯罪事実と犯人が誰であるかは発覚しているが、単に犯人がどこにいるのか分からないだけでは発覚する前とはいえません。
また、申告した相手(警察官など)がたまたま犯罪事実を把握していなくても、捜査機関の誰かが把握していれば、すでに発覚した後として扱われます。 -
(4)自身の処罰を求めていること
犯罪の申告には、単に事実を話すだけでなく、「自分が罪を犯したので、きちんと処罰されたい」という気持ちがあることが必要です。
自身の責任を否定すれば自首にはあたりません。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、自首が成立しないケースの具体例
自分では「自首したつもり」でも、実際には法律上の要件を満たさず、自首と認められないこともあります。
自首が成立せず、単なる出頭として扱われるのは次のようなケースです。
・指名手配され、逃亡している途中に観念して出頭した
すでに捜査機関が事件と犯人を把握しているため、「発覚前」の条件を満たしません。
・出頭したものの、犯罪事実を告げない、または罪を否定している
自分の罪を申告し、処罰を求める意思がなければ自首とされません。
・出頭要請を受け、任意の取り調べ中に罪を認めた場合
取り調べの過程で罪を認めても、それは「出頭」に該当します。
・ほかの犯罪を隠すために一部の犯罪のみを申告した場合
本当は複数の事件を起こしていたのに、軽いものだけ話した場合などは、自首の要件を満たしません。
自首が成立しなくても、出頭したという事実が「逃亡・証拠隠滅のおそれがない」と評価される可能性はあります。
このような姿勢は、検察官による不起訴の判断や、裁判での量刑判断において有利な事情として考慮されることがあります(刑事訴訟法第248条/刑法第66条)。
自首の成立にこだわる前に、「どう行動するのが一番いいか」を弁護士と一緒に考えていくことが大切です。
4、自首の効果は? どのくらい刑を減軽できる?
「自首をすると刑が軽くなる」と聞いたことがあるかもしれません。
実際、法律では自首した場合に“刑を減らせる”という規定があります。
とはいえ、どのくらい軽くなるのか、どんな場合に認められるのかは気になるポイントです。
ここでは、自首による刑の減軽の仕組みや、そのほか期待できる効果について解説していきます。
-
(1)自首すれば刑が減軽される可能性がある
自首が成立すれば、裁判で「刑を軽くすることができる」として法律に定められています(刑法第42条)。
このように自首は、法律上の刑の減軽事由に該当しますので、自首の要件を満たせば、起訴されて有罪になったとしても刑が軽くなる可能性があります。
ただし、条文上は「減軽することができる」と書かれており、実際に刑が減軽されるかどうかは裁判官の判断に委ねられています。
自首が成立したとしても刑の減軽が認められないケースもあるのです。
一方で、自首したことで「反省の意思がある」「逃げていない」と評価され、結果的に刑が軽くなる事例あります。
刑の減軽が認められるかどうかは、“自首そのもの”だけでなく、事件後の対応や態度も大切なポイントです。 -
(2)自首すればどのくらい刑が減軽される?
自首によってどれくらい刑の減軽できるかについては、法律でルールが設けられています。
主な刑の種類ごとに、自首による刑の減軽の効果を以下の表にまとめました。
刑の種類 自首による刑の減軽の効果 死刑 無期拘禁刑または、10~30年の拘禁刑 無期拘禁刑 7~20年の拘禁刑 有期拘禁刑 上限・下限を1/2に減らす(例:6年→3年) 罰金 最大額・最少額を1/2に減らす 拘留 最長期間を1/2に減らす(例:30日→15日以下) 科料 金額の上限を1/2に減らす
たとえば、有期拘禁刑(例:3年~7年など)であれば、その「上限と下限」を半分にすることができます。
死刑や無期懲役といった重い刑の場合も、軽い刑に変更される可能性があります。
※あくまで「法的に可能な上限」であり、実際にどの程度刑が減軽されるかは、事件の内容や本人の反省の程度などをふまえて裁判官が判断します。
自首に加えて、被害者への謝罪や示談などの行動があれば、より大きな刑の減軽が期待できることもあります。
5、自首で刑の減軽以外に期待できること
自首には「刑を軽くする可能性」以外にも、さまざまな効果が期待できます。
状況によっては、人生における大きな選択を左右するほど重要なポイントになることもあるため、以下のような効果についても知っておくとよいでしょう。
-
(1)逮捕を避けられる可能性がある
自首すると、「逃げたり、証拠を隠したりするおそれがない」と判断され、逮捕されない可能性が高まります。
そもそも逮捕とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合になされる強制手続きです(刑事訴訟法第199条、刑事訴訟規則第143条の3)。
自らの罪を申告して処罰を求めている以上は逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されることが多いため、結果として逮捕を回避できる可能性が高まるのです。
逮捕されなかった場合は「在宅事件」として扱われ、被疑者は日常生活を送りながら自宅から通う形で取り調べを受けることもあります。 -
(2)実名報道を避けられる可能性がある
事件が報道されるかどうかは報道機関の判断によりますが、一般的には自首した場合のほうが、逮捕された場合よりも実名報道されるリスクは低くなるでしょう。
特に自首によって逮捕を免れた場合は、著名人の事件など社会的な影響力が大きい事件でない限り、報道を避けられる可能性は高くなります。 -
(3)不起訴になる可能性がある
犯罪の事実が明らかな場合でも、検察官は「犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により」、起訴しないと判断することができます(刑事訴訟法第248条)。
自首したことは、犯罪後の反省的な対応として評価され、不起訴につながるケースも少なくありません。
特に、被害者との示談や謝罪がある場合には、不起訴の可能性がさらに高まります。 -
(4)執行猶予がつく可能性がある
裁判で有罪となった場合でも、自首により刑が軽くなれば、執行猶予がつく可能性も出てきます。
執行猶予が認められると、猶予期間中に罪を犯さないことを条件に、刑務所には行かずに社会生活を送りながら更生の機会を与えられます。
仕事をやめずに済む可能性もあり、社会復帰が円滑に進みやすいでしょう。
6、自首により刑が減軽されやすいケース
自首が成立すれば刑が減軽される可能性はありますが、必ず罪が軽くなるというわけではありません。自首による刑の減軽は、裁判官が法定刑よりもさらに軽い刑罰が適切だと判断した場合に行われます。
実際には、事件の内容やその後の対応によって「刑が減軽されやすいケース」と「されにくいケース」があります。
まずは、「刑が減軽されやすいケース」の例を挙げます。
-
(1)被害回復に積極的な姿勢がある場合
被害者がいる犯罪では、被害者との示談が刑の減軽を受けるにあたって重要な要素となります。
被害者との間で示談が成立している、あるいは謝罪や弁償の意思を示している場合は、反省の意思があると評価されやすく、刑の減軽を考慮してもらえる可能性が高くなります。 -
(2)犯行の背景に酌量の余地がある場合
たとえば、認知症の妻の介護を長期間ひとりで担っていて、老老介護の負担から妻を殺してしまったなどの事案では、法定刑の下限でも重すぎると判断される可能性があります。
このように社会的・心理的に同情の余地がある事情があるケースでは、事案に応じた適切な刑罰を科すために刑が減軽されやすいといえるでしょう。 -
(3)捜査に協力的な態度を示している場合
自首後に犯行を素直に認め、警察の捜査に対し全面的な協力をしているケースでは、本人の反省の態度が明確であり、刑を軽くする判断につながりやすいといえるでしょう。
-
(4)自首で減軽された裁判例
事例 ①:大阪地裁堺支部令和3年1月8日判決
被告人は、強盗目的で高齢者宅に押し入り、被害者をガムテープで緊縛するなどの暴行を加えて、現金やキャッシュカードなどを強取したことなどを理由として、住居侵入、強盗、窃盗、電子計算機使用詐欺罪で起訴されました。
裁判では、被告人が自首したことや反省していること、社会復帰後は更生支援団体の支援が受けられる予定であること、若年であることなどが考慮され、検察側の求刑が懲役6年のところ、自首減軽により懲役4年の実刑判決となりました。
事例 ②:京都地裁令和4年7月6日判決
被告人は、早朝10名が居住する施設の2階の自室で、布団が燃え上がるまでライターで何度も火を付けて施設の一部を焼損させた現住建造物等放火の罪で起訴されました。
裁判では、被告人が自首をしたこと、被害者が重い処罰を望んでいないこと、自閉スペクトラム症および統合失調症が犯行動機の形成に影響していること、精神病院への入院が内諾されていることなどの事情を考慮し、検察側の求刑は懲役5年でしたが、自首減軽により懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡されました。
7、自首により刑が減軽されにくいケース
自首の要件を満たしていたとしても、以下のようなケースでは、自首減軽がされない可能性が高いでしょう。
-
(1)発覚が確実な状況での自首
警察により事件の捜査が進んでおり、犯人の特定まであと少しというところまで迫っている状況での自首では、刑が減軽されない可能性があります。
なぜなら、自首による刑の減軽は、犯罪の捜査や犯人の処罰が容易になったことへのインセンティブという意味合いがあるため、このようなケースではインセンティブを与えるに値しないからです。 -
(2)計画性があり悪質な犯罪の場合
計画性があり悪質な犯罪の場合、そうでないケースに比べて重く処罰される傾向があります。あらかじめ準備して犯行に及ぶなど、強い犯意や社会的影響の大きさが認められると、たとえ自首しても刑の減軽の幅は限定的になります。
-
(3)犯行による被害が重大な場合
人命が失われるなど、結果が深刻な事件では、量刑も重くなる傾向があります。
このようなケースでは自首が成立したとしても、法定刑を下回る刑罰にするべき事案ではないとして、自首による刑の減軽が認められにくいでしょう。 -
(4)自首減軽されなかった裁判例
事例 ①:最高裁令和2年12月7日決定
被告人は、被害者の嘱託を受けることなく殺害した後、嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを遺体のそばに置き、警察に電話をかけ犯罪事実の申告をしました。
裁判では、虚偽の犯罪事実の申告で自首が成立するかどうかが争点となりましたが、裁判所は、事実を偽って申告している場合には自己の犯罪事実を申告したとはいえないため、自首は成立しないと判断され、懲役19年(求刑20年)の刑が確定しました。
事例 ②:東京地裁令和4年6月7日判決
本件は、時計店からの1200万円超の腕時計窃盗と、高齢者から詐取したキャッシュカードによる現金引出等の特殊詐欺事案が含まれ、被害総額は約3000万円に及んでいます。
被告人は、警察官からの職務質問を受けた際に、侵入窃盗事件について自ら犯罪事実の申告をしたものの、捜査機関は、侵入窃盗事件について被告人が犯人であるとの疑いを抱いていたことからこれが自首にあたるのかが争点になりました。
裁判所は、侵入窃盗事案については、被告人が自供する前に犯人の点を含めて捜査機関に発覚していたことが認められるとして自首の成立を否定しました。
なお、弁護人からは捜査報告書に「被疑者不詳に対する建造物侵入、窃盗被疑事件」との記載があることからまだ犯人は発覚していなかった旨の主張がなされましたが、裁判所は、捜査書類を作成した捜査官個々の認識ではなく、捜査機関全体における犯人特定のための捜査活動の進捗状況に基づき判断すべきとしています。
裁判では、犯行の計画性・組織性を指摘する一方、前科がないことや両親の協力、被告人の反省等も考慮し、懲役5年(求刑7年)が言い渡されました。
このように、自首をしただけではなく、その後にどのように対応するかも重要な判断材料になります。
刑の減軽の可能性を高めるためにも、弁護士のサポートを受けながら、適切な対応を取ることが大切です。
8、自首する前後の流れ
実際に自首をすることになったら、どんな流れで手続きが進むのでしょうか?
以下では、自首前の準備から、警察での手続き、そしてその後の対応まで、一般的な流れをご紹介します。
-
(1)自首に向けた準備
自首をする際は、事前の準備も大切です。
突然の逮捕や留置の可能性もあるため、最低限の備えをしておくと安心です。
・家族や会社への連絡をしておく
自首したその日のうちに逮捕にいたれば、家族や会社の人などと連絡が取れなくなってしまうので、自首する旨や今後のことを指示しておくとよいでしょう。
・身の回りの物の準備
必要に応じて、留置場内で使う現金や着替え、身分証明書なども準備しておきましょう。
・弁護士に相談・同行を依頼する
弁護士が同行することで、手続きがスムーズになるほか、逮捕の回避にもつながる場合があります。
自首は事件が発覚する前にすることが大切なので、自首を決意したらすぐに弁護士に相談の上、管轄の警察署などに連絡し、自首の手続きを進めるのが賢明です。
警察署と日程を調整したうえで自首する場合もあります。 -
(2)自首の方法
自首は、最寄りの警察署・交番・警察相談窓口などで行うことができます。
自首の方法には口頭と書面の2つあり、どちらでも受理されます(刑事訴訟法第241条・第245条)。
・口頭による自首
直接警察官に対して「自分が〇〇という罪を犯しました」と申し出て、犯行時の状況などを説明します。口頭による自首では、警察官が自首調書を作成することで受理となります。
・書面による自首
書面でする場合は自首の経緯や事件について書かれた自首報告書を作成して警察署に持参して提出します。簡単な説明を求められる場合もあります。 -
(3)捜査機関による取り調べ
自首をしても、緊急逮捕などを除き、その場ですぐに逮捕されるとは限りません。
事件や犯人が発覚する前に自首しているのだから、自首をした段階では証拠が不足しており逮捕状を請求できないためです。
まずは、任意の取り調べが行われるのが一般的です。 -
(4)逮捕または在宅捜査
取り調べや裏付け捜査の結果、証拠がそろったと判断された場合は、次のいずれかの対応が取られます。
・通常逮捕(任意からの切り替え)
自首の当日や、数日後に、通常逮捕されるケースもあります。
これは、警察が裁判所に逮捕状を請求し、発付されたうえで本人を逮捕する方法です。
取り調べの結果から罪を犯したと疑われ、証拠隠滅または逃亡のおそれがある場合には、逮捕状が請求され、通常逮捕される可能性があります。
・在宅捜査
逮捕の要件を満たさなかった場合は、逮捕されずに捜査が進められます。これを「在宅事件」といいます。
特に軽微な犯罪(例:30万円以下の罰金・拘留・科料にあたる罪)の逮捕は定まった住居を有しない場合などに限られているため、在宅捜査となる可能性が高くなるでしょう(刑事訴訟法第199条1項ただし書き)。
9、自首のポイント・注意点|刑の減軽のためにできること
以下では、自首により刑が減軽されるためにできることと自首の注意点について説明します。
-
(1)自首する前に弁護士に相談する
自首を検討中の方は、自首をする前に弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に相談をすることで、自首をした後の流れや取り調べに対するアドバイスが受けられますので、自首後の取り調べで不利な供述調書を作成されてしまうリスクを軽減することができます。
また、被害者がいる場合には、被害者との示談交渉も任せられますので、示談成立による刑の減軽も期待できます。 -
(2)弁護士に自首に同行してもらう
自分ひとりで警察に自首するのが不安だという方は、弁護士に自首に同行してもらうことも可能です。
弁護士が自首に同行することで、捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅のおそれがないということをアピールすることができ、逮捕を回避できる可能性が高くなります。
また、自首後の取り調べは、弁護士が同席することはできませんが、自首に同行した弁護士が警察署内で待機していますので、いつでも取り調べを中断して弁護士にアドバイスを求めることができます。 -
(3)できるだけ早く自首する
自首は、捜査機関が犯人および犯罪事実を把握する前に行わなければなりません。
そのため、自首をお考えの方は、できるだけ早いタイミングで行動することが大切です。
迷っているうちに発覚してしまい、自首の効果を失ってしまうケースもあるため、判断は慎重かつ迅速に行いましょう。 -
(4)取り調べでは、冷静に事実を正直に話す
警察で自首が受理されると、警察官による取り調べが行われ、自首調書が作成されます。
自首による刑の減軽の可能性を高めるには、取り調べでは事件に関することを正直に話し、捜査に協力する姿勢を示すことが重要です。
ただし、警察官による取り調べでは、警察官の誘導に乗ってしまい自分の認識とは異なる内容の調書が作成されてしまうリスクがありますので、弁護士のアドバイスを踏まえて冷静に対応するようにしましょう。 -
(5)被害者への謝罪や賠償の意思を示す
自首による減軽の可能性を高めるには、自首以外にも被害者への謝罪や賠償の意思を示すことが、よりよい結果につながる大きな要素になります。
被害者との示談交渉が成立すれば、有利な情状として考慮してもらえますので、逮捕や起訴を回避することや、起訴されたとしても執行猶予判決や量刑の減軽を受けられる可能性が高くなります。
そのため、自首だけではなく、被害者との示談交渉も並行して進めていくようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、直接会いに行かずに謝罪や示談の意思を伝えることができるため、トラブルを避けながら誠意を示すことができます。
10、自首にまつわるQ&A
以下では、自首にまつわるよくある質問とその回答を紹介します。
Q、親告罪の場合、被害届が出ていなければ自首しなくてもいい?
親告罪で被害届が出ていなかったとしても、自首を検討すべきです。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴されない犯罪のことです。
被害者から告訴が行われていなければ、警察は捜査を開始しませんので、その時点では自首をしても意味がありません。
しかし、被害届が提出されれば、警察は捜査を開始しますので、将来の告訴に備えて自首をするという点では意味のある行動になります。
Q、自首してその場で逮捕されるのはどんなとき?
自首をしたとしても、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるケースでは、その場で逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕を回避するには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されるために、自首する際に事件に関する証拠を持参して、警察に提出することが有効です。
Q、もうすぐ時効の場合は自首しないほうがいい?
公訴時効が成立すれば、刑事責任は問われません。
ただし、時効直前でも逮捕・起訴されるケースもある上、逃げ続けることには精神的な負担もあります。少しでも罪を軽くするなら自首をした方がよいケースもあります。
このように自首をすべきかどうかは慎重な判断が求められますので、一度弁護士に相談してから方針を決めるべきでしょう。
Q、家族と一緒に自首してもいい?
自首に家族が同伴することもできますので、自分ひとりで自首をするのが不安だという方は、ご家族に一緒に来てもらうとよいでしょう。
なお、法的なアドバイスを希望される場合は、弁護士の同行がおすすめです。
Q、弁護士に同行してもらう費用はどのくらいかかる?
弁護士に自首同行してもらうための費用は、依頼する弁護士によって異なります。
そのため、具体的な弁護士費用については、直接弁護士事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、初回電話相談60分無料です。
お気軽にお問い合わせください。
11、自首は慎重かつ迅速な判断が重要
自首は犯罪の事実および犯人である旨を、捜査機関に発覚する前に申告することで成立します。すでに捜査の対象となってから出頭しても自首にはあたりません。
自首が成立すれば刑が減軽される可能性がありますが、法的に自首が成立する状況かどうかは難しい判断を要する問題なので、自首を検討する場合はあらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。
そもそも犯罪が成立するのか、自首よりも示談を優先させるべきかなど、自首に関するアドバイスも得られるでしょう。
自首するべきかどうかでお困りの場合はベリーベスト法律事務所へご相談ください。
刑事事件の解決実績豊富な弁護士が的確にアドバイスし、自首の同行や示談などもサポートいたします。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。