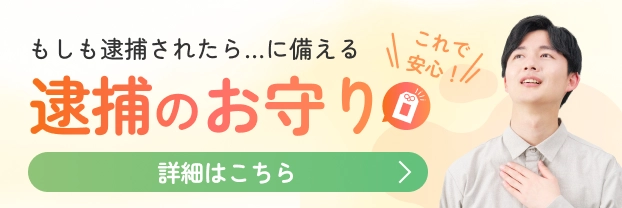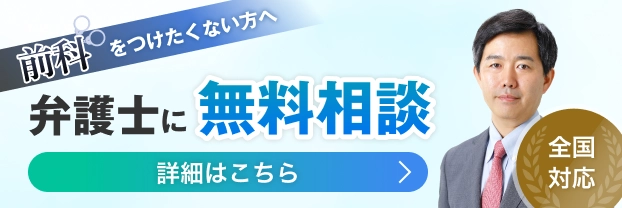- その他
- 起訴されたら
起訴とは|刑事事件で起訴されたらどうなる? 不起訴との違いや流れ


刑事事件における「起訴」とは、検察官が裁判所に対して、犯罪の被疑者を処罰するよう求めることです。
刑事事件に関する報道などで、「起訴」という言葉をよく耳にしますが、起訴された場合、犯罪の被疑者はこれからどのような取り扱いを受けるのでしょうか。また起訴されると確実に有罪判決となり、前科がつくことになるのかも気になります。
本コラムでは、刑事事件における「起訴」について、意味や不起訴との違い、起訴されるまで・起訴されてからの流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。あわせて不起訴処分を目指すためにできる具体的な活動内容も見ていきましょう。
1、起訴とは
刑事事件で起訴されたらどうなるのかを知るために、まずは起訴とは何かを知っておきましょう。
-
(1)刑事事件における「起訴」とは?
起訴とは、検察官が犯罪の被疑者への刑罰を求めることです。「公訴の提起」ともいいます。日本では検察官だけが起訴できる権限を持っています(刑事訴訟法247条、起訴独占主義)。警察官は犯罪の捜査をしても起訴することはできません。
また、刑事事件を起こしても、全員が起訴されるわけではありません。検察官は被疑者が罪を犯したことが証拠などから明白であり、刑罰を与えるのが相当だと判断した場合のみ起訴します。 -
(2)起訴の種類
起訴には逮捕・勾留されて身柄拘束を受けたまま行われる場合のほかに、在宅起訴や略式起訴と呼ばれるものがあります。
在宅起訴とは、被疑者の身柄を拘束せずに自宅で日常生活を送れる状態のままで起訴することです。刑事事件を起こすと必ず逮捕されると思う方もいるかもしれません。しかし、逮捕は被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合などにおいて行われます。そのため、警察の捜査は逮捕しないまま進めるのが基本です。被疑者は在宅のまま警察・検察官から呼び出されて取り調べを受け、捜査が終了した時点で検察官によって起訴・不起訴を判断されます。
略式起訴とは、起訴後の手続きを正式の刑事裁判によることなく、書面のみの審理で簡易的に処理するものをいいます。この手続きでは、裁判所は、100万円以下の罰金または科料を科すことができるとされているので、対象になるのは、比較的軽微な事件です。
略式起訴された場合は公開の刑事裁判にかけられず、罰金または科料を言い渡されます。裁判所で刑事裁判が行われる場合と違い手続きが迅速に終わるため被疑者の負担は軽くなりますが、被疑者の同意が条件なので裁判で無罪を主張したり反論したりすることはできません。
2、不起訴とは? 起訴との違い
不起訴とは、検察官が被疑者を起訴しないことです。起訴は、検察官が裁判を求めることですが、不起訴は検察官によって裁判は必要ないと判断されることです。
そのため、不起訴になった場合は刑事手続きがそこで終了し、刑罰を受けることも前科がつくこともありません。
不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの理由がありますが、圧倒的に多い理由は「起訴猶予」です。令和5年版の犯罪白書によると、令和4年の不起訴人員47万9092人のうち、起訴猶予となったのは41万9846人です。
起訴猶予とは、罪を犯したのが明白であっても、被害の程度が軽い、被害者と示談が成立した、深く反省していて更生の可能性が高いなどの諸事情を考慮してあえて起訴しないとする処分です。このように検察官による起訴猶予処分を認める法制度を起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)といいます。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、起訴されたら被疑者はどうなる?
起訴された被疑者は被告人へと立場が変わり、刑事手続きが進行します。
-
(1)刑事裁判が終了するまで身柄拘束は続く
逮捕・勾留されたまま起訴された場合、刑事裁判中も引き続き身柄の拘束を受けます。起訴前の勾留(被疑者勾留)は最長で20日間ですが、起訴後の勾留(被告人勾留)は原則として2か月です。ただし1か月ごとの更新が認められているため、実質的に制限がありません。公判回数によっては何か月・何年も勾留が続いてしまいます。
刑事裁判で無罪判決や罰金、執行猶予つき判決が言い渡されると被告人の身柄は釈放されますが、実刑判決が言い渡されるとそのまま拘置所に連行されます。逮捕・勾留されたまま起訴されたら、一度も身柄を釈放されることなく刑務所へ収監されるケースもあるのです。 -
(2)ただし起訴後は「保釈請求」が可能に
逮捕・勾留に続いて起訴後も身柄拘束が続けば、被告人の心身の負担は大きく、日常生活への影響も甚大です。そこで起訴後は被告人に保釈請求する権利が認められています。
保釈とは、一定の要件を満たし、かつ保釈金を預けるのと引き換えに、裁判で判決が出るまで一時的に身柄を釈放される制度のことです。
保釈は「権利保釈」「裁量保釈」「義務的保釈」の3種類がありますが、もっとも多いのは「権利保釈」です。以下の不許可事由に該当しなければ必ず保釈が許可されます(刑事訴訟法第89条)。
- 死刑・無期・短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯した
- 前に死刑・無期・長期10年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪で有罪判決を受けた
- 常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
- 証拠隠滅をするおそれがある
- 被害者や証人などに危害を加えたり怖がらせたりするおそれがある
- 氏名または住居が分からない
-
(3)在宅事件の場合は身柄拘束されない
在宅事件の場合、起訴されてから1~2週間程度で裁判所から起訴状の謄本などが届くので、指定された期日に出廷して審理を受けます。起訴後も身柄拘束を受けずに裁判期日にのみ出廷し、審理の結果を待つことになります。
ただし裁判で実刑判決が下された場合は、判決後に身柄を拘束され、刑に服さなければなりません。在宅事件であっても実刑判決を受ける場合はあります。在宅事件という理由だけで不起訴になったり、刑が軽くなったりするわけではないことは知っておかなければならないでしょう。 -
(4)略式起訴された場合はどうなる?
身柄事件で略式起訴された場合は罰金の納付により即日で身柄を釈放されます。
在宅事件で略式起訴された場合は自宅に罰金刑の略式命令書が届くので、検察庁に罰金を納付することで、事件は終了します。 -
(5)就業規則によっては会社を解雇されるおそれもある
起訴された段階では裁判で有罪が確定したわけではないので、会社は従業員が起訴されたことのみを理由に解雇することは原則としてできません。
しかし犯罪行為が明白な場合や会社の対外的な信用を失墜した場合などには、就業規則の規定にもとづき解雇されてしまう場合があります。また逮捕から継続して身柄を拘束され長期欠勤になっている場合も、そのことを理由に解雇されるおそれがあるでしょう。
したがって、刑事事件の被疑者となった場合はできるだけ早い段階から不起訴処分を目指して活動すること、万が一起訴されたら早急に保釈を請求して身柄の釈放を目指すことなどが重要です。
4、事件後から起訴されるまでの流れ
起訴されるまでの流れや起訴までに要する日数などについて、身柄事件・在宅事件に分けて解説します。
-
(1)身柄事件の場合
身柄事件とは逮捕、勾留などにより被疑者の身柄を拘束した状態で捜査を進める事件をいいます。身柄事件の場合、逮捕から起訴されるまでの期間は最長で23日間です。このあいだ、被疑者は警察署の留置場などに留置され、自由な行動は制限されます。
逮捕された被疑者は48時間以内に警察の取り調べを受け、身柄付きで事件が検察官へ送致されます。送致から24時間以内に、今度は検察官からの取り調べを受け、検察官によって引き続き身柄拘束が必要かどうか、「勾留」の必要性が判断されます。
ここまでの72時間では起訴・不起訴を判断するための材料がそろわないケースもあります。その場合、検察官は、引き続きの身柄拘束の必要性があるとして、裁判官に対して身柄拘束の延長を求める「勾留」を請求します。裁判官が勾留を認めると、被疑者は原則10日間、延長でさらに10日間、引き続き身柄を拘束されます。勾留が満期を迎えるまでに、検察官は起訴または不起訴を判断します。 -
(2)在宅事件の場合
被疑者の身柄を拘束しない状態で捜査が進められる事件を在宅事件といいます。被疑者は自宅で社会生活を送りながら起訴・不起訴の決定を待つことになります。
在宅事件になるのは次のようなケースです。
- 逮捕されなかった場合
- 逮捕・送致されたが検察官が勾留請求しなかった場合
- 勾留請求されたが裁判官が勾留を認めなかった場合
- 逮捕・勾留されたが勾留の途中で身柄を釈放された場合
在宅事件でも身柄事件と同様に警察が検察官に事件を送致し、検察官が起訴・不起訴を決定する流れで手続きが行われます。ただし在宅事件の場合は被疑者の身柄拘束がともなわないので、捜査資料や証拠書類のみが検察官へ送致されます。マスコミなどが使う書類送検という言葉は、在宅事件における送致のことを指しています。
また在宅事件では、身柄事件のように起訴・不起訴を判断するまでの制限期間が法律上定められていません。したがって在宅事件の場合、身柄を拘束されていないため被疑者の身体の負担や社会生活への影響は軽減されますが、起訴・不起訴までの制限期間がない分、事件が長期化する可能性があります。いつ事件が解決するか分からないため精神的に不安な状態が続く可能性があるでしょう。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
5、起訴されたら有罪? 起訴後から判決確定までの流れ
起訴されてから判決が確定するまでの流れを解説します。起訴されたら必ず有罪になってしまうのか、起訴後の有罪率も含めて確認しましょう。
-
(1)略式起訴された場合
身柄事件で略式起訴となる場合は、事前に検察官から略式手続きの説明と略式起訴に異議がないかどうかの確認があります。被疑者がこれに同意する場合、略式手続きの告知手続書および申述書に署名・押印します。
勾留の満期日かその直前の平日に検察官が裁判所に対して略式起訴を行い、数時間後に裁判所が略式命令を発付します。略式命令とは略式手続きにおける裁判のことです。略式命令が下ると勾留の効力が失効するため身柄の拘束を解かれますが、そのまま警察官と一緒に検察庁の徴収窓口に行き、罰金を支払うことになります。
通常は検察官が被告人の家族に罰金を持参するよう連絡しておきます。
在宅事件で略式起訴になる場合は、警察から検察官へ事件が送致されたあと、検察庁から呼び出しを受けます。検察庁では身柄事件と同様に略式手続きについての説明と異議がないかの確認があり、同意する場合は手続きの書面に署名・押印したあとに自宅に帰されます。同意から約1週間後に略式起訴され、さらに2週間程度で簡易裁判所から略式命令の書類と罰金の納付書が郵送されてきます。納付書にしたがい罰金を支払って手続きは終了です。
なお、略式起訴は被疑者が罪を認めて同意することが要件なので、略式起訴された場合は必ず有罪になります。罰金や科料の刑罰であっても前科がついてしまうため、同意するかどうかは慎重に判断しなければなりません。罪を犯していない場合や自分の言い分を主張したい場合などは、同意する前に弁護士に相談することが大切です。 -
(2)公判請求(通常起訴)された場合
正式裁判で事件が審理されることになった場合は、起訴から1か月半~2か月程度で初公判が開かれます。初公判までのあいだ、被告人が捜査機関から取り調べを受けることは原則としてありません。弁護士と面会する、弁護士が証人や証拠の収集を行うなど裁判に向けた準備期間となります。
保釈請求をするのも起訴後のこのタイミングです。保釈が認められなければ身柄拘束を受けたままとなります。保釈が認められると自宅に帰され、初公判の期日を待ちます。
公判期日では書面の証拠調べや証人尋問・被告人質問などがあり、検察官と弁護人の弁論手続きを経て審理が終了します。罪を認めている自白事件でかつ複雑な事情がない事件では、審理が1回で終了し、そこから約2週間後の第2回期日で判決の言い渡しとなるケースが多いでしょう。
一方、否認事件や重大事件の場合は何回も公判が開かれ、結審までに年単位の時間がかかることがあります。 -
(3)起訴後の有罪率は約99%
起訴されても必ず有罪になるわけではありませんが、その確率は極めて高いと言わざるを得ません。検察統計「審級別 確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」(令和4年)によれば、総数20万572人のうち、無罪・免訴・公訴棄却・管轄違いを除いた20万181人が何らかの有罪判決を受けています。有罪率は99.8%です。
これだけ高い有罪率になっているのは、検察官が確実に有罪になると見込んだ事件だけを起訴していることの表れであると考えられます。また、えん罪を防止するために起訴すべきかどうかは慎重に判断されているともいえます。
起訴後の有罪率から分かるとおり、起訴された場合に無罪判決を得るのは非常に難しいことです。起訴されるとほとんどのケースで有罪となり、前科がついてしまうと考えておくべきです。
したがって前科を回避するには、起訴されないこと、つまり不起訴処分を得るための活動が極めて重要です。犯罪白書によれば、令和4年における刑法犯の起訴率は36.2%と、起訴後の有罪率と比べればはるかに低い率になっており、不起訴処分を目指すことの重要性が分かります。
6、不起訴処分を獲得するためにできることとは?
では、不起訴処分となるためには具体的にどのようなことができるのでしょうか?
-
(1)事件について反省の態度を明確に示す
罪を犯したのが事実であれば、不起訴処分のうち起訴猶予を目指して活動します。刑事訴訟法第248条によると、起訴猶予とするかどうかは次のような要素をもとに判断されます。
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重
- 犯罪の情状
- 犯罪後の情況
このうち、事件のあとに変えられる要素は「犯罪後の情況」です。具体的には、反省文を提出する、贖罪寄付を行うなどして反省の態度を明確にします。被疑者が深く反省していると更生に期待できるため、起訴猶予の可能性が高まるでしょう。
また、検察官は再犯のおそれがあるかどうかを重視するため、家族が監督を誓約する、依存症の専門施設で治療を開始するといった再犯防止策を示し、再犯のおそれがないことを具体的に主張することも大切です。 -
(2)被害者がいる場合は示談の成立を目指す
被害者がいる事件では、被害者との示談が成立していることが起訴猶予となる可能性を高める要素となります。検察官は起訴・不起訴の決定に際して被害者感情も含めて判断するため、被害者に謝罪と被害弁済を行い、被害者が「被疑者を許す」という宥恕(ゆうじょ)意思を示した事実を評価する可能性が高いのです。
また仮に起訴された場合でも、示談の成立は裁判官が量刑を判断する際にも考慮されます。判決に執行猶予がつく可能性を高められるため、示談は継続して進めることが大切です。
しかし示談を成立させることは簡単なことではありません。被疑者本人やその家族から直接被害者に示談交渉をしようとしても、加害者からの連絡は拒否される可能性が高いでしょう。またそもそも被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉をすることはできません。
そのため、示談交渉は弁護士に一任すべきです。弁護士なら、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手できる可能性があるほか、弁護士が対応することで被害者が示談交渉に応じてくれやすくなり、交渉を効果的に進められる可能性が高まります。 -
(3)まずは早めに弁護士へ相談を
不起訴処分に向けたこれらの活動は、被疑者やその家族だけでできるものではありません。法律の知識や刑事弁護の経験がなければ、具体的に何をすればよいのか、何が有効な活動になるのかを判断できない場合が多いです。そのため事件を起こしたら早急に刑事弁護の経験のある弁護士へ相談し、法律の知識にもとづき活動を進めてもらうことが大切です。
身柄事件では逮捕から起訴されるまでに最長で23日間しか時間がありません。在宅事件でもいつ起訴されるかを検察官が教えてくれるわけではないため、気づけば起訴されたという事態を避けるためにも迅速な対応が必要です。
また、早めに弁護士に相談しておくと、仮に起訴されてしまった場合でも保釈請求をスピーディーに進められます。一時的にとはいえ判決までのあいだ身柄を釈放されれば、会社や学校に通うこともでき、社会生活上の影響をできるだけ抑えることができます。
保釈請求は被告人やその家族にも認められていますが、法律上の保釈要件を満たす旨を的確に伝えなければ保釈されないため、弁護士から保釈請求するのが最善です。
さらに弁護士は刑事裁判で不当に重い量刑を言い渡されないよう、被告人にとって有利な裁判資料を集めて的確に主張・立証する、被告人質問の準備をするなど、判決が確定するまで被告人のために活動します。
7、まとめ
刑事事件で起訴されたら極めて高い確率で有罪判決を受ける可能性があり、有罪判決となれば前科がついてしまいます。前科がつけば会社を解雇されるなど不利益を被るおそれがあります。
そのため刑事事件の被疑者になった場合は、まずは不起訴処分を目指して具体的な活動を進めることが大切です。不起訴処分に向けた活動は被疑者本人やご家族だけでは難しいため、早急に弁護士へ相談しましょう。
刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力を尽くします。起訴を防ぐには時間との勝負でもあるので、できるだけお早めにご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。