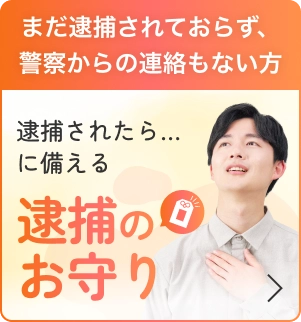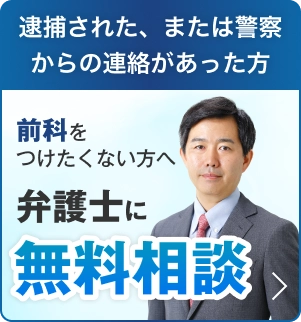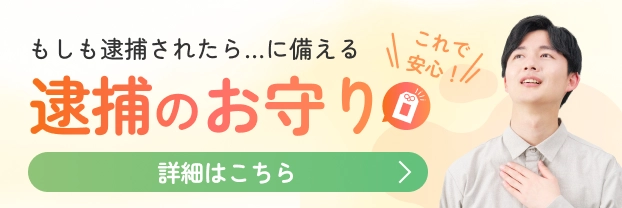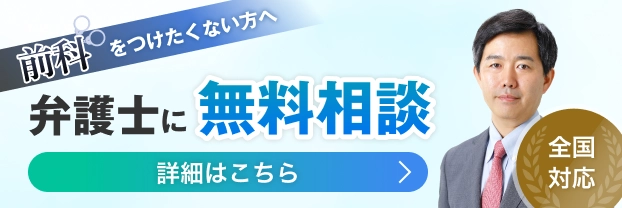- 少年事件
- 補導
警察に補導されたらどうなる? 補導歴は将来の就職などに影響する?


警察庁の統計によると、令和元年における、全国の不良行為少年の補導人員は37万4982人、このうちもっとも多かった理由は深夜徘徊の21万691人でした。
補導はどのようなことを意味する言葉なのでしょうか?
この記事では、補導の概要や対象者、補導される場合の具体例、就職などの将来に及ぼす影響について弁護士が解説します。また、補導のかいなく子どもが刑法犯として逮捕された場合の対応方法についても見ていきましょう。
1、補導されるのはどんな場合? 補導の意味とは
「補導」について、少年が対象となること以外、詳しいことを知らない方も多いでしょう。ここでは、補導の定義や種類、対象者について説明し、具体的にどのような場合に補導されるのかに関しても解説します。
なお、少年とは少年法2条で20歳に満たない者、と定義されており、少年少女のことをいいます。
-
(1)補導とは
補導とは、少年の非行を防止するため警察が行う、あらゆる活動の総称です。
刑法や刑事訴訟法などの法律に規定された概念ではなく、「少年警察活動規則」という国家公安委員会の規則で定められています。
補導には、繁華街などの犯罪が起こりやすい場所において適宜行われる「街頭補導」と、対象者の改善が見えるまで指導を続ける「継続補導」の2種類があります。「補導」といえば、一般には街頭補導を指します。 -
(2)補導の対象者
街頭補導の対象となる少年は、非行少年、不良行為少年、被害少年、要保護少年です(少年警察活動規則6条、2条5号から8号)。
非行少年 - 犯罪少年(14歳以上で、罪を犯した少年)
- 触法少年(14歳未満で、刑罰法令に触れる行為をした少年)
- 虞犯(ぐはん)少年(保護者の監督に従わない、家庭に寄りつかない、犯罪性のある人や不道徳な人と交際している、
いかがわしい場所に出入りしている、などの事由があり、性格や環境から見て将来犯罪や刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年)
不良行為少年 - 非行少年には該当しないものの、飲酒や喫煙、深夜徘徊などの行為(不良行為)をしている少年
被害少年 - 犯罪などで被害を受けた少年
要保護少年 - 児童虐待を受けた児童
- 保護者のいない少年
- その他児童福祉法による福祉の措置やこれに類する保護の措置が必要と認められる少年


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
2、補導歴、非行歴の将来への影響は?
自分の子どもが補導された場合、補導された事実が将来どのように影響するか非常に気になるところです。似た概念である、非行歴との違いと、補導歴が及ぼす将来への影響について解説します。
-
(1)補導歴と非行歴の違い
補導歴とは、犯罪以外の理由で少年が警察に補導された履歴のことです。
これに対して、非行歴とは、非行少年として検挙または補導された履歴のことです。
補導歴は不良行為少年などについての補導した履歴、非行歴は非行少年として検挙や補導された履歴とイメージすればよいでしょう。
補導歴は少年が20歳になると破棄されます。しかし、非行歴は前歴として警察の記録に残ります。 -
(2)審判への影響
補導歴および非行歴の情報は警察が管理し、警察が検察や裁判所に提出する書類を作成する際に参照されることがありますが、情報が一般に公開されることはありません。
ただし、繰り返し補導された場合には影響が生じます。過去に補導歴や非行歴のある少年が再び補導された場合に、逮捕するか、家庭裁判所に送致して審判を開くか、さらにはどのような保護処分をするかという判断をする際には過去の補導歴、非行歴も考慮されます。
また、非行歴は20歳を過ぎても前歴として残るので、成人してから犯罪をすると、非行歴を踏まえた処分がなされます。 -
(3)就職への影響
補導歴や非行歴に関する情報は一般には公開されません。非行歴は前歴ではありますが、前科ではないので、履歴書の賞罰欄へ記載する必要はありません。資格制限などもありません。
もっとも、非行が原因で退学処分などを受けた場合には、なぜ退学になったのか面接で経緯を聞かれる可能性があります。そこで虚偽の回答をすると経歴詐称といわれてしまうため、弁護士に相談して対策を練る必要があるでしょう。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、少年が犯罪をして逮捕された場合には、早めに弁護士に相談を
警察や保護者による補導のかいなく、少年が犯罪を行い発覚した場合、その後はどうなるのでしょうか?少年事件の特徴や、弁護士の活動内容を解説します。
-
(1)逮捕された後の手続きとは
警察官によって逮捕された場合には取り調べを受け、検察へと送致されます。(罰金刑以下の犯罪嫌疑の場合には、検察ではなく家庭裁判所に直接送致されます。)
少年の場合、検察官は取り調べをしたのち、事件を家庭裁判所に送致します。そして家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に収容するか、在宅観護とするか、審判不開始とするか判断します。少年鑑別所では2週間から最長8週間にわたって各種検査や調査がなされ、家庭裁判所による少年審判が行われます。
少年審判にて裁判所が下す処分は不処分、保護処分、知事又は児童相談所長送致、検察官送致決定の4つです。保護処分には保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致の3種類があります。
調査、審判を行った上で、裁判官がいずれの処分にするかすぐに決めることが困難と判断する場合は、相当の期間(おおむね3か月から4か月)、少年を家庭裁判所調査官の観察に付す試験観察となることもあります。 -
(2)少年審判は非公開
成人の刑事裁判は原則として公開されますが、少年審判は非公開です。
少年審判では、非行事実だけではなく、少年の置かれている環境や少年自身の特性、さらに家族の生活実態などプライバシーに関することに踏み込んだ調査・審理がなされるからです。これらの事実が一般に公開されると、その後の少年の更生を阻害するおそれがあるため、非公開とされています。
従って、少年審判は少年、保護者、裁判官、調査官、書記官、必要に応じて検察官や付添人(多くは弁護士)、保護観察官などのみで行われます。事案によっては、被害者の申し出により、傍聴が許可される場合や、審判状況の説明がされることがあります。 -
(3)少年事件における弁護士の活動
少年事件の場合、弁護士は、不当に重い処分を受けないよう、また早期に身柄解放されるよう付添人として弁護活動を行います。
- 弁護士であれば、補導や逮捕直後から面会ができる 補導・逮捕直後は、たとえ家族であったとしても、すぐに本人と面会できるとは限りません。この点、弁護士であれば、身柄拘束をされたとしても、すぐ少年と面会ができます。面会時には、今後の見通しや取り調べについての助言を行います。
- 早期に身柄が解放されるよう働きかける 弁護士は、検察官に勾留(身柄拘束を続けること)請求を行わないよう、あるいは裁判官に勾留請求を却下するよう働きかけます。裁判官により勾留決定がされた場合には準抗告を行うことができます。
- 示談を行う 被害者がいる場合には弁護士が少年の代理人として示談交渉を行います。
特に少年事件の場合、成人と比べ、どのような事実が重要かについて十分に理解できない場合が多く、捜査機関側の誘導に乗ってしまいやすい傾向があります。そこで、弁護士が供述の重要性や黙秘権の意味、効果などについて丁寧に説明します。
また、鑑別所での観護措置についても決定を行わないよう裁判官に働きかけ、実際になされた場合には不服申立てが可能です。
少年事件の示談は、成人の刑事事件のように、処分の軽減に直結するわけではありません。しかし被害の回復に努め被害者と真剣に向き合うことで、更生できる可能性を示し、重すぎる処分を避けることが期待できます。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
4、まとめ
「自分の子どもが補導をされた」と連絡を受けた場合、これからどうなるのだろうと動揺する方が大半でしょう。しかし、大切なのは補導された事実を受け止め、少年がどのように更生していくか考えることです。
弁護士は、身柄拘束時の本人へのフォローや、非行からの更生計画を作成するなど、ご家族を支え、少年本人を更正させる助けとなれます。
不当に重い処分を受けることを避けるためにも、自分の子どもが補導された場合には、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。ベリーベスト法律事務所では、刑事事件専門チームを作り、多くのご相談を受けてきました。ご依頼いただいた場合には、刑事事件専門チームと担当弁護士が、全力を尽くします。


- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。